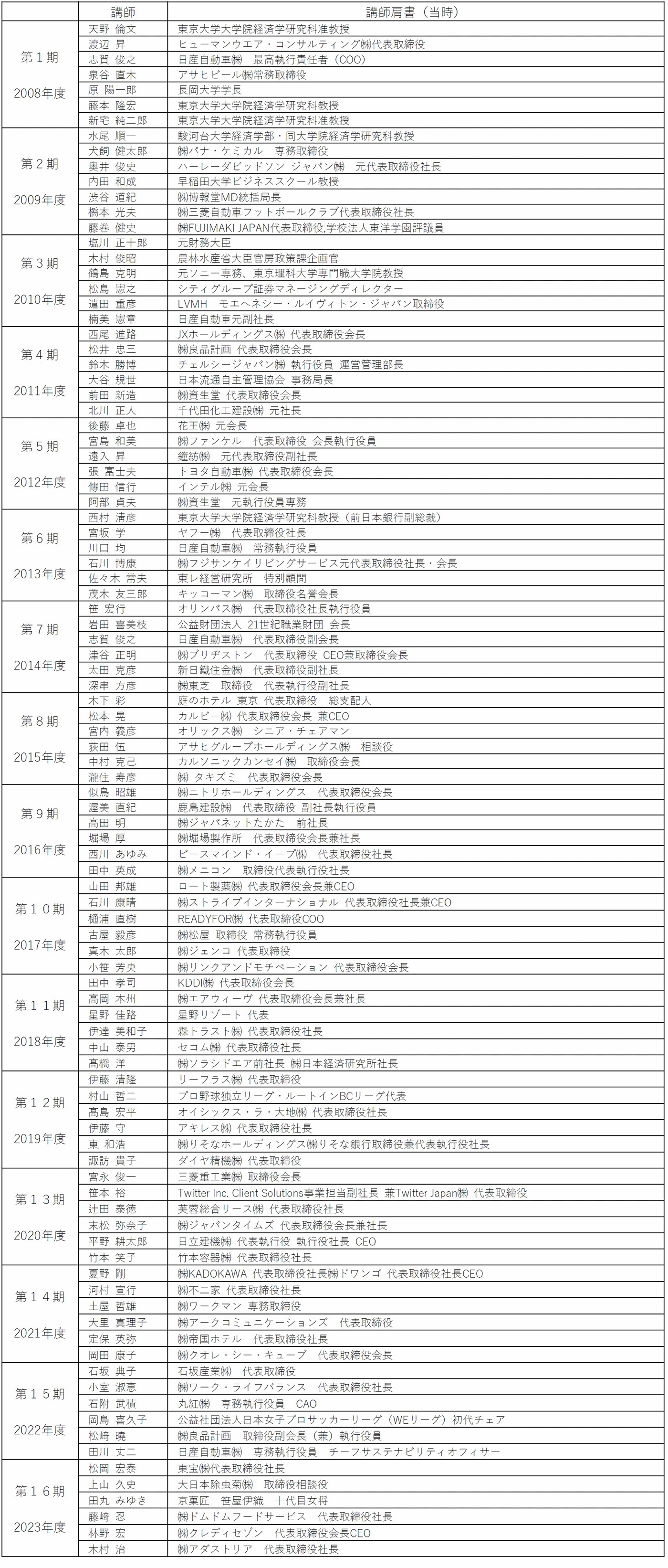現代経営研究会について寄稿してほしいとの依頼を受けたが、私が知るところは限られている。企画段階の構想も知らないし、私が辞めた後に発展した(今日の隆盛の)理由も知らない。私が関係した当時の思い出といっても極めて個人的なもので、特に自動車業界出身のため製造業のことになってしまうことをご容赦いただきたい。

現代経営研究会は、大学院が発足した2008(平成20)年に大学院創設と同時に始まった。私は、第3期(2010年度)から第10期(2016年度)まで研究会の主査を務めた。研究会を立ち上げた当時の深海博明研究科長や土屋守章主査がお亡くなりになったため、私が代わって寄稿することになったようだが、できるだけ正確に記しておきたいと思って、連絡がとれる範囲で数名の先生に取材した。
藤枝省人初代学部長の下で学部創設に尽力された石川勝先生からは現代経営学部創設の理念についてお聞きした。初代大学院専攻長の田中秀穂先生には研究会のルーツについてうかがった。初期の研究会でたくさんの講師を呼んで下さった鍋田英彦先生には講師の方々をめぐるエピソードを教えてもらった。
1. 現代経営の意味
現代経営研究会について述べる前に、「現代経営」の意味について記してきたい。現代経営学部が創設当初に掲げていた教育理念にも関係があるし、書き残しておくべきと思うからである。
石川先生によると、現代経営学部の当初の教育には少なくとも2つの特徴があったという。
第1は、経営理論を学ぶだけでなく経営的なwisdom(叡智)を習得してほしいということである。そのため、教科書の理論では学びきれない教育手法として「ケースメソッド」をさまざまな科目で導入しようとしたそうである。
畳の上でいくら水泳の練習をしても泳げるようにならない。これを「畳の上の水練」と言うが、私もこの言葉を聞いた覚えがある。「水練」とはいかにも古い言い回しだが「経営理論だけ勉強しても十分でない」という意味であったに違いない。
第2は、経営学とともに経済学を重視したことである。そのために、慶應義塾大学を定年退職後、他大学に行かれていた佐々波楊子先生や深海博明先生をお招きし、一年生から経済学を必修にしたということである。
藤枝初代学部長は、ハーバード大学大学院を修了後、慶應のビジネススクールやフランス、フィリピン、ハワイの大学で教えておられたが、おそらく同窓の佐々波先生や深海先生に声をかけたのだと思う。ご存じのように、佐々波先生は緒方貞子さんの従姉妹でハーバード大学を出て国連でも活躍された著名な国際派経済学者で、深海先生は科学技術庁原子力委員会の専門委員としても活躍された資源エネルギー研究の第一人者である。
藤枝先生は「企業は大海の小舟である。小舟が荒波を乗り越えて目的地に到達するには、船長は大海の動きを読めなければいけない」と言われたらしい。ここで言う大海とは経済社会全体のことで、その理解のために経済学の知識が大事と考えておられたのであろう。
現代経営学部が発足する当初、現代経営学部の英語名をどうするかということで議論があったそうである。藤枝先生と佐々波先生で検討された結果、“modern business administration”では不十分ということで“comprehensive business administration”という名称になったというが、この名称から教育理念が読み取れる。つまり、社会を俯瞰する大局的な視点を持ちながら、包括的な叡智を動員して経営を実践してほしいという願いが込められていたのだと思う。
しかし、これらの教育方針は少し理想が高すぎたかもしれない。たとえば、ケースメソッドは、ハーバード大学のビジネススクール(大学院レベル)で生まれた教育技法で、社会経験の少ない学部生にとってはハードルが高かったようである。また、経済学も抽象的な概念や数学を必要とする理論が多く、授業を始めてみたら、担当教員も学生も大変だったに違いない。
学部創設の年に「経済学の授業がわからない」と言ってきた学生がいた。私は「偉い先生なんだから有り難く聞いておいた方がいいよ」と言ったのだが、その時、その学生は「どんなに偉くても自分にわからないことを教えるのは間違っている」と食ってかかってきた。
そんなこともあって、私が学部長時代には皆さんに相談しながら「ケースメソッド」ではなく「ケーススタディ」と言い換えて、学部の方向を少し変えてみた。カリキュラム体系は変えなかったが、抽象的概念や理論を補完する方法として「ケース」を取り込もうとしたのである。
ここでちょっと固い話だが、ケースメソッドとケーススタディの違いについて述べておきたい。ケースメソッドは教室の中で、教員と学生が話し合いながら、自分たちなりの解決法を考えていくものだが、ケーススタディは、実際の出来事を事例として教育の材料に生かすもので、抽象概念や理論を説明する場合に使う。つまり、実務経験がないとディスカッションに加われないケースメソッドに対して、具体的なものから抽象的なものへ導くケーススタディは学部生に向いているように思ったのである。
また、「現代経営」の意味も、「現在進行形(~ing)」の経営課題を考えるという意味を加えた。英語で言えば、comprehensiveやmodernというよりcurrentやexistingというニュアンスだろうか。
この現代経営研究会でも「今起きている経営課題は教科書だけでは学べない」と言ったり「現在進行形の課題に取り組んでいる経営者から話を聞きたい」と書いたりした。それがよかったかどうか。その是非は後世の評価にゆだねるしかないだろう。いや、今回、100年史を編纂するにあたって現代経営学部創設当初の思いの一端を聞くことができたので、ここに記しておきたい。願わくは今後の学部運営の参考になればと思っている。
2. なぜ「研究会」なのか
次に、現代経営研究会が、なぜ「講演会」や「公開講座」でなく「研究会」なのかという点に触れておきたい。このことは、前述の現代経営学部の理念とも関係するし、(当時の)人文学部が立ち上げた公開教養講座との違いを説明ためにも必要と考えるからである。
今回、現代経営研究会のルーツが、中西寅雄先生が1948(昭和23)年に始めた「企業研究会」にあることがわかった。中西先生は東大に「経営経済学」を作った方だそうで「企業研究会」は田中秀穂先生が東レにいた30歳代に参加した頃には大規模な異業種交流会になっていたとのことだった。田中先生はもう90歳近いので今から60年近く前のことである。
田中先生は、東レ時代にこの研究会に大いに刺激を受けたため、土屋先生が来られるのを機に東洋学園大学でも同じような研究会をやってみたいと考え、研究科長だった深海先生に提案したそうである。今回驚いたのは横浜でお会いした時に入手した企画書の日付が2002年だったことである。現代経営学部が発足したのがちょうど2002年だから田中先生は学部創設時(現代経営研究会が始まる5年も前)から案を温めていたことがわかった。人文学部の公開講座が教育研究資源を地域社会に還元しようとしていたのに対して、現代経営研究会は企業経営者を明確に意識して相互研鑽を目的にしていたのである。
そうした経緯もあってからか、地域経営者と共に学ぶ研究会として、最初の2年間は土屋守章先生が主査をなさっていた。土屋先生は東大を定年で退官された後、他大学で教鞭をとっておられたが、新設大学院にはマル合教員が必要だったので三顧の礼でお呼びしたと聞いている。マル合教員とは学位論文の指導ができる教員のことで、新設の大学院は文科省の審査を受けるため、著名な学者を招聘することがある。
土屋先生は穏やかなお人柄であったが、学問の世界では妥協を許さない方であった。たとえば、日本的経営が三種の神器(年功序列/終身雇用/企業内組合)論に傾いていた頃に、「企業カプセル」という切り口で独自の経営論を展開していた。企業が社員に生活の保障を与え、人間関係的な居場所を作り、同質的な価値観を押し付けている状況をカプセルと呼んだのである。制度という「仕組み」だけではなく「経済(生活の保障)/社会(居場所)/規範(愛社精神)」という全く異なる次元で社員が会社に取り込まれていると喝破したスケールの大きな経営論だった。
今から振り返ると、日本企業が世界を席捲していた80年代に、その後の失速を見越していたわけで、もし土屋先生が生きておられたら「ガラパゴス化」などという言葉は生まれず「カプセル化」という言葉が一般化していたかもしれない。
また、たくさんのお弟子さんを育てたことでも有名で、例えば、インテグラル(擦り合わせ)型とモジュラー(組み合わせ)型を対比して世界を唸らせた藤本隆宏先生も土屋先生の門下生のおひとりだった。
そんなわけで、当初の研究会は、現在のようなフェニックスホールではなく、1304教室といった小さな教室で、藤本先生のような東大の教授陣も招いていた。土屋先生は名著『ハーバード・ビジネス・スクールにて』(中公新書、1974)にもあるように、ビジネススクール流の経営学、つまりケースメソッドの極北を極めた人だったで、現代経営研究会でもフリーディスカッションを重視されていた。
例えば、私がコメンテーターになった時、準備していたコメントを終えて座ろうとしたら「井原さん座らないで」「君のコメントから議論を始めよう」と言われた。私が引き継ぐようになって「質問は1回に限る」などと言ってしまったので今では恥じ入っている。つまり、講演者はケースの提示者であって、コメンテーターはディスカッションの起動者だったのである。
これが、第1回と第2回の報告書がない理由である。研究会の成果は研究会の中にあって、参加者は聴いたこと話したこと、あるいは対話の間にあることを持ち帰っていた。言うまでもなく、これこそがケースメソッドである。つまり、現代経営研究会の当初の構想は、現代経営学部の教育理念とぴったり合っていたことになる。
3. 講演会形式への転換
ところが、土屋先生から主査を引き継いだ私は戸惑った。私には、土屋先生のように議論をリードする技量はないし、東大の教授陣のような百戦錬磨の研究者を相手に甲論乙駁の議論を収束させていく自信がなかったからである。

そこで、私はここでも方向を変えてしまった。第1は、一般市民の方々にも参加してもらう公開講座のような形にしたのである。大学は知的プラットフォームであるべきで、せっかく外部から立派な講師をお招きしているのだから会員企業で独占してはいけない…というようなことを言ったが、これは言い訳だった。
第2は、質疑応答の部分を懇親会に変えてしまった。その際、研究会の質疑応答の伝統は懇親会で引き継ぎたい…というようなことも言った。これも詭弁で、懇親会ならば、ケースメソッドのように丁々発止の議論にはならないだろうから、私でも司会役が務まるのではないかと踏んだわけである。
その結果、後になって教職員の皆さんにご苦労をおかけすることになった。アイデアレベルでは簡単なことと思ったのだが、実行面では大変だったことに後から気がつくことになったのである。
例えば、それまで学内や会員企業だけでよかった研究会を広く周知しなければならなくなって、ポスターを大学の内外に掲示し、文京区の広報誌にも掲載し、大横丁商店街にある読売新聞の販売店にも協力してもらって無料で新聞にチラシを入れることになった。だが、実際に動くのは広報や総務の職員だった。夏の暑い日も冬の寒い日も、ポスターとセロテープを持って地域の掲示板を回ってくれたのだが、掲示を町会長に許可してもらうために、地域のお祭りに休日を返上して参加していたことをずいぶん後になって知って頭が下がった。
懇親会でも、会場づくりで多くの職員に迷惑をかけることになった。私は、近くの酒屋さんに安くしてもらったり、酒屋さんの店頭にポスターを貼ってもらったり、先頭を切って走ったつもりだったが、すべてフォローしてくれたのは職員の皆さんだったらしい。
報告書を作るのも、簡単なようで大変だったと思う。教員の皆さんにコメンテーターになってもらったり、講演記録をお願いしたりしたが、録音して原稿に起こし講演者のOKをもらうのは大変だったに違いない。
後で、張さんのところで、第三者の視点という話をするが、私の場合、相手(職員)の立場に立つことすらできなかったと反省している。
4. 講師の方々の思い出
最後に当時の思い出を書き残しておきたい。私が主査と務めていた間に、合計48人にもなる方々にご登壇頂いた。ひとりひとり貴重なお話をして下さった大切な方々で、個別に取り上げることは紙幅の関係でできないことが残念である。ただ今回、鍋田先生から第4期(2011年度)にご登壇しただいた松井忠三(当時㈱良品計画代表取締役会長)さんの話をいただいたので、それに乗じて私なりの感想も付け加えてみたい。
鍋田先生によれば、松井さんは「創業者タイプの経営者」だという。なぜなら、西友がスタートした「無印良品」をユニクロ並のブランドに育て、停滞していたアパレル市場を活性化させ、新たなグローバル市場の構築を実現させたからである。その際、旧来型の組織風土と商慣習に思い切ったメスを入れたが、そのために、売れ残った膨大な衣料品の不良在庫を処分した。
松井さんは、バイヤー全員を集め、自分たち自身が選び抜き買い揃えた商品をあえて目の前に置き、焼却処分されるところを正視するように命じたそうであるが、そこまでするには胆力が要る。組織の問題を部門長のせいにするのは簡単だが、組織改革のためには「みんなの責任としてみんなに知らしめる」必要がある。当然、反発も予想されるので腰を据えて深沈と刀身を振り下ろさなければならない。身を切る覚悟と言う人もいるが、返り血を浴びる覚悟の方がもっと重たいかもしれない。
鍋田先生は第5期(2012年度)にトヨタ自動車の張富士夫(当時トヨタ自動車㈱代表取締役会長)さんも講師として呼んで下さった。張さんは東大剣道部出身だが「剣道の試合では、審判員の視点を持つことが大切です」とおっしゃった。これは講師控室で聞いた私だけの秘密だったがこの機会に書き残しておきたい。
私は意外な答えにはっとして、すぐに日産の米国進出のことを思い出した。私が勤めていた80年代、日産はトヨタより早くテネシーに現地工場を立ち上げ、社長としてフォードから副社長をスカウトして経営を任した。いわゆる米国流の経営を取り入れたわけである。ところが、張さんが社長になったケンタッキーの工場は後から来たのにあっという間に大きくなった。
つまり私は、剣道の話を聞いた時、自分の視点で相手を見るだけでなく、自分と相手の間にいる審判員の視点を持って経営されたのではないかと理解した。きっと、日本的経営でも米国流の経営でもない、第三の経営をなさったのではないかと考えたのである。
己も相手も客観視する第三の視点を持つためには日々の訓練が必要だと聞いて心が震えた。それ以来、時々、その言葉を思い出して身を正すことがある。現代経営研究会は「今」を生きる経営者から「ライブ」で話を聴ける場だが、直に聞いた「生の話」は一生忘れないものである。
鍋田先生は、松井さんと張さんの共通点についてスポーツで培った謙虚さ、信念、胆力などをあげてくれた。もしかしたら、藤枝先生がおっしゃった「経営的なwisdom(叡智)」には、そういったものも含まれていたのかもしれない。
しかし、時代は大きく変わりつつある。「水練」に始まって体育会系の話に終わってはいかにも男臭くていけない。私達が研究会を主宰していた頃は重厚長大型企業の男性経営者が多かったが「重たすぎる」研究会をしなやかに受け止めて下さったのが八塩圭子先生である。
1年ほど引継ぎのために進行役をお願いしたが、淡々と議論を進めながら誰にも目配せした華のある司会ぶりで、さすがテレビ東京きっての名アナウンサーだった方だと感心させられた。公正取引委員会で活躍された鵜瀞惠子先生にもお世話になった。両先生の幅広いご人脈も手伝ってか、その後の研究会は、サービス業、IT企業、起業家、女性経営者、老舗企業経営者と多士済々である。集合型の講演会はコロナで大変だったに違いないが、オンラインも駆使して見事に乗り切って下さった。一般参加者を科目等履修生として単位認定したり、他大学の学生の参加も得たりして大きく発展したと聞いている。最近の報告書を読むと「不確実な時代だからこそ経営理念やSDGsのような考え方が不動の道標になる」という記述があって、現代経営研究会が、学部創設当初の狙い(「大海の動きを読む」海図の役割)を達成していることにも気づかされた。
こうして振り返ると、深海研究科長、土屋主査、田中(秀)専攻長が始めた研究会は、鍋田先生はじめ多くの方々の人脈によって大きくなり、八塩先生や鵜瀞先生に引き継いでいただき今日あることがよくわかる。もちろん、江澤雄一先生や一ノ渡尚道先生のサポートなしには立ち上げることができなかったし、現在の愛知太郎理事長、辻中豊学長、田中巌学部長、畔上秀人研究科長はじめ理事や評議員の皆さんのご理解があって続けて来られたわけで、本当にたくさんの方々が支えてくださっている研究会だとつくづく思う。これからも講師の方々、学生や参加者の方々、教員職員の方々をはじめたくさんの方々の協力を得て、現代経営研究会がますます発展していくことを願ってやまない。
現代経営研究会講師一覧(2008年~現在)