1. はじめに-本学の認証評価について
認証評価制度は、学校教育法に基づきすべての大学が7年以内に1回、文部科学大臣の認証を受けた評価機関(認証評価機関)による評価を受けるよう義務付けられたものだ。大学等の教育研究の質の担保を図るため、組織運営や教育研究活動等の状況を定期的に確認することが目的とされている。
当然ながら本学としても認証評価機関による評価を受けなければならず、最初の認証評価を受けたのは制度施行から7年目の2010(平成22)年度であった。7年以内に1回受けるよう定められている中で、第1クールの最終年に何とか滑り込んだという訳だ。
そこからまた7年後の2017(平成29)年度に2回目の評価を受け、無事に大学基準に適合していると認定されている。現在は、この時の結果に基づく認定期間(2018年4月1日~2025年3月31日)の途中にあるということになるが、来年度でこの認定期間が終了するため、既に次回の受審準備を大学評価専門委員会と所管部署である法人本部企画部を中心に進めているところである。
現在は所属を外れているので次回に向けた準備に直接的には関与できていないが、過去2回の受審の際、私はいずれも企画部の職員として事前の手続きや報告書の作成、実地調査受け入れの準備等、認証評価に関わる一連の業務に携わらせていただいた。このことは、大学が国や社会から求められていることを改めて理解するよい機会となり、その後の自身の職務において大いに役立っていると思っている。ご指導下さった先生方、共に業務にあたってくれた同僚にも恵まれ、本当によい経験をさせていただいた。

柴鉄也先生
その経験があることから、私が今回この原稿を書くようにと仰せつかった。ただ本当は、過去2回の認証評価のことを私以上に深く理解しておられ、この原稿執筆者として私よりずっと相応しい方がいる。当時から本学にいらっしゃる教職員の方々はお気づきのことと思う。柴 鉄也先生である。
1回目の認証評価受審の際、柴先生には学長補佐のお立場に加えて大学評価専門委員長の職をお務めいただき、また2回目の受審の際は既に定年退職後の特任教授のお立場でありながら、前回に引き続き大学評価専門委員長をお引き受けいただいた。大学評価専門委員長として様々な学内調整から報告書作成に至るまで奔走され、2回とも本学が「適合」の評価を獲得できたのは間違いなく柴先生のご尽力のおかげだと思っている。本学の認証評価を振り返る時にはどうしても欠かせない方だと言っていい。
だからこそ、その柴先生に本学の認証評価について改めて語ってほしかったし、この原稿をお書きいただきたかったが、それは叶わなかった。療養中でいらした今年1月、大変残念なことに先生はご逝去なされてしまったのだ。
報を聞いた時、本当に驚きショックだった。先生の退職後もやり取りしていた年賀状がある時から来なくなり、どうしているだろうと思っていた矢先のことだった。この約2年前に1回目の認証評価受審時の学長 一ノ渡 尚道先生がご逝去なされ、その報を伝える電話で話したのが柴先生との最後の会話になってしまった。認証評価作業が終わった時、先生がご退職になられた時、何度もお礼を伝えたつもりだが、逝ってしまわれる前にもう一度お礼を言えなかったことを悔やんでいる。
今回、100年史編纂委員会からは、学園の歩みを振り返る上でのトピックの1つとして「認証評価」にまつわるコラムをと言われているが、認証評価を振り返る上ではどうしても柴先生との思い出が中心になってしまう。どうかご理解いただきたい。
2. 認証評価作業への取り組み
(1) 大学基準協会に受審することにした理由
さて、本学の最初の認証評価は、一ノ渡学長の号令の下、前述のように柴先生を中心として取り組みが始まった訳だが、当然ながら受審する2010(平成22)年度より前から様々な準備が進められた。その中で最初にやらなければいけなかったのは、受審する認証評価機関を決めることだった。
当時、大学を対象とした認証評価機関は3機関あり、この機関は厳しいらしいとか、あの機関は適合評価を簡単に出すらしいなど、受審した各大学の感想や噂レベルの話まで様々な情報が飛び交う中で、最終的には一ノ渡学長を中心とした大学評価委員会の議論を経て決定した。果たして、3機関の中から財団法人大学基準協会(現在は公益財団法人)を選択したのだが、事前の話では、大学基準協会の評価基準が最も厳しく不適とする大学も多いということだった。それにもかかわらずこの機関を選択したのは、「難しいところにこそチャレンジして、厳しい評価基準をクリアした大学だと社会に認知してもらおう!」という学長の心意気からだった。そう笑いながらお話し下さった一ノ渡先生のお顔が忘れられない。心からご冥福をお祈り申し上げる。
(2) 2条評価
認証評価と言えば今では大学関係者にはよく知られた制度となっているが、法律施行から数年経っているとはいえ、当時の本学内での認知度は低かった。その中で、とにかく教職員に認証評価という制度を理解してもらうことが必要だということになり、受審の前々年度にあたる2008(平成20)年の夏、大学基準協会から講師を招いて説明会を実施した。
この説明会を実施する前は、大学が受審する評価のことを「第三者評価」とか「自己点検・評価」といった呼び方をする人も多かった。「認証評価」という言葉が学内で定着できたのもこの説明会が機会となったのでないかと思っている。
説明会の中では、7年に1度の認証評価だけでなく、常日頃から自己点検・評価を積み重ねていくことの重要性についても解説があった。それを受け、本学でも自己点検・評価を実行していくこととし、毎年度末に各学部やセンター、委員会、事務局の各部署から報告書を提出いただき、企画部で取り纏めることとなった。
他大学で発行しているものを参考にしながら様式のサンプルを作成し、各部門の責任者に執筆を依頼したが、やはり初めての取り組みなので執筆者の筆は遅々として進まない。ここでも柴先生が必要性を説きながら原稿の催促をして下さり、すべて揃ったのは当初の予定を1ヶ月以上過ぎてからだった。そうして本学最初の「東洋学園大学自己点検・評価報告書」は発刊された。
少し余談になるが、本学で取り組んでいるこの自己点検・評価のことを「2条評価」という独自の名称で呼んでいること、またその理由をご存じだろうか。
実はこの呼称の名付け親は柴先生である。前述のように当時は大学評価に関するさまざまな名称が学内に飛び交っていて、また認証評価用の報告書も「自己点検・評価報告書」という名称にするよう定められていたので、大学が取り組む点検・評価と大学が受審する点検・評価の区別が何が何だかわからなくなっていた人が多かった。そこで、2つの点検・評価をしっかり区別して認識してもらうため、本学が毎年度取り組む自己点検・評価を学内では「2条評価」と呼ぶようにしよう、というのが柴先生のアイデアだった。
ご存じの方は少ないかも知れないが、この“2条”というのは「東洋学園大学学則」の第2条を指している。学則の第2条には、「本学は、教育研究水準の向上を図り、前条の教育目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。」と定められている。柴先生はここからこの呼称を思い付き、学内では積極的に使うようにしておられた。
ただ、この呼称を使うようになって暫くした後、「認証評価と区別しやすくするために2条評価って言いだしたけど、『にんしょうひょうか』と『にじょうひょうか』では音が似ていて聞き取りづらいね。」と先生自身が仰っていたのは今も笑い話だ。
(3) 報告書作成
そんな2条評価を認証評価本番のシミュレーションとしてやってみた訳だが、自分たちを点検・評価し、2ページずつの報告書にまとめるという作業でさえそれなりの時間がかかったのだから、点検・評価項目と基準が厳格に定められた認証評価の報告書作りがどれ程のものになるのか、この時点で大体覚悟はできていた。
大学基準協会が定めた評価項目のすべてをここに列記するのは避けるが、大学の理念・目的、教育課程・教育内容、学生の受け入れや教職員の体制等、1回目の受審時には15、2回目の受審時には10の評価項目が設定されていた。これらの項目ごとに評価基準がさらに細かく示されていて、この基準に対して本学がどういう状況にあるのか、報告書に記述していく訳である。
報告書を本学で作成していくにあたっては、先ず各評価項目の内容に必要な情報を持っている学部・学科、センター、委員会、事務局に担当を割り振り、各組織の長に原稿執筆の依頼をした。当然ながら1つの評価項目の内容は1組織の情報だけでは足りないので、複数の組織の長に依頼することになる。例えば、教育課程のことについて書こうとすれば、少なくとも3学部の教育課程についてそれぞれ記述が必要になるため、3人の学部長にお願いするといった具合だ。
ただ、これでは依頼者の数も回収する原稿も多くなる。その上、集まってきた原稿は、それぞれの評価基準に沿って記述されているといっても執筆者によって重点の置き方も違うし、文章の表現も様々だ。実は1回目の受審時はこの点でとても苦労した。当初は、集まった原稿をそれぞれ繋ぎ合わせ、全体を通して少し文面を整えればよいくらいに考えていたのだが、いざ集まってみると、それぞれの原稿の分量や表現のギャップは思いのほか大きかった。
12月中旬には大学基準協会に報告書の草案を一度提出する必要があるので、執筆者に書き直しをお願いしている時間はない。そこで、草案提出までの一カ月の間に柴先生と企画部でこれらの繋ぎ合わせと調整の作業を行うこととなった。報告書の全体を通して文章の表現・テイストが統一されている必要があることから、柴先生が先ず一通りこの作業を行いながら不足している部分を加筆し、整った部分から私が再度点検、“てにをは”や文末表現等をチェックしていくという流れだ。
1回目の受審時、最終版の報告書は278ページにも及んだ。柴先生が行って下さった分量調整や表現のギャップを埋める作業は、相当な労力と時間がかかったはずだ。
また、当然ながら報告書には嘘や事実と異なることを記述する訳にはいかないので、その内容にはすべて根拠を示す必要がある。図表を示すだけで済むこともあれば、既存の成果物等を探し出して別途用意しなければならないこともあり、これらの根拠資料を一つ一つ報告書の本文と結び付けて整理しなければならないのも手間のかかる作業であった。併せて本学の組織、設備、学生募集状況、学生・教職員数、財務状況等に関する基礎的なデータを揃える作業にも多くの時間を要した。主にこれらの作業は企画部の同僚職員が担当し、事前に余裕をもって準備してくれたお陰で締切前に慌てることなく提出することができた。私の手が行き届かなかった点をサポートして下さり本当に感謝している。
このような過程を経て何とか提出要件を満たした報告書を完成させ、最終版を3月末までに提出することができたのだが、これで認証評価の作業が終わりという訳ではない。この後、実地調査が待っているのだ。
(4) 実地調査
報告書を提出した後、認証評価に関する作業は少しの期間落ち着くのだが、そろそろ学生が夏季休暇に入ろうかという頃、大学基準協会より実地調査に関する通知が届く。1回目、2回目ともに10月に調査を行うという知らせだった。実地調査が行われることは事前にわかっていたし時期も大体予想していたのだが、いざ具体的に準備を始めるとなると決めなければいけないこと、揃えなければいけないものが多く、再び認証評価対応が中心の日々に戻っていくことになる。
実地調査は、学長・教職員との意見交換、授業参観、施設・設備の見学、学生インタビューといったものが主な内容だ。意見交換は協会が指定した複数の評価項目について行われるので、それぞれに対応できる教職員に依頼しなければならないし、学生インタビューは教職員が同席することができないので、対応をしっかり任せられる学生を先生方に推薦してもらうということも必要だった。授業参観、施設見学等もあわせ、事前の調整作業は多方面に渡った。
実地調査の準備で忘れられないのは、当日本学にやってくる委員の“事前調査”だ。調査に来る委員は大学基準協会から委託された会員各大学の教職員なのだが、実地調査時期を知らせる通知が届いた時点では本学担当の委員の人数だけが示されており、1回目の受審時が3名、2回目の受審時が5名だった。
調査日が近くなってから協会より委員の所属と氏名が明らかにされる。そうすると、柴先生は所属大学のHP等からそれぞれの委員に関する情報を集め、例えば、この委員は研究分野が経済学だから主に現代経営学部のことについて聞いてくるだろうとか、所属大学で教務委員を務めているから教育課程のことについて詳しいはずだとか、いろいろと予想を立てる訳である。
ただ、既に報告書に書いたことを変えられる訳ではないし、当日までの時間も殆どないため具体的な対策がとれるわけでもなく、結局は「まあ当日少し気にしておこうね」というくらいの話で終わるのだが、心配事は少しでも減らしておきたいという柴先生らしいエピソードだと思う。
実地調査の当日は、時間をかけて事前準備をしていたこともあり思いのほかうまく進んだように覚えている。意見交換の中で新たに準備するものを指示されたようなことはあったが、大きなハプニングはなく終了することができた。
ただ、やはり当日の現場は、各イベントが実施されている場に必ず誰かが同行しなければならなかったり、関係各所との連絡に走り回ったりと、文字どおりドタバタだった。特に1回目の受審時には、2日間の実地調査の中で流山キャンパスも見学するという行程が組まれていた。調査する委員を流山キャンパスに引率するだけでなく、学生インタビューの参加学生の集合確認と打ち合わせ、見学する各施設との調整等、当日はとにかくてんやわんやだった記憶しかない。
(5) 評価結果
実地調査が終了すると本学でやれることはもう殆どない。12月に評価結果の「委員会案」が届くので内容を確認し、必要があればその委員会案に対する意見申し立てを行うが、それ以降は最終結果が出るのをじっと待つだけである。
最終の評価結果が本学に届いたのは、年度が終わろうとする3月中旬になってからだ。既に委員会案を見ていたので心配はしていなかったが、正式に『評価の結果、貴大学は本協会の大学基準に適合していると認定する。』という文言を見た時はやはりほっとした。柴先生にもすぐに文書を見ていただくと、いつものようににっこり笑って「よかったね」とだけ仰った。いつも静かにお話になる方なので特に大げさな表現をすることはなかったが、それでもとても嬉しそうな笑顔で「よかった。よかった。」と何度も仰っていた。
年度が明け、前期オリエンテーション等が落ち着いてきた頃、認証評価作業にずっと関わってきた私を含めた職員2人を柴先生が食事に誘ってくださった。一番大変な思いをされたのは柴先生なのに、ご苦労様だったねと言って私たちを慰労してくださったのだ。
場所は大学近くのホテルにある高級レストラン。先生はコース料理まで予約してくださっており、乾杯の後は次から次へと運ばれてくる料理に舌鼓を打った。その合間に3人で沢山の話をした。この2年間で経験した苦労や失敗も、「適合」の評価結果が出ているこの時にはもうすべて笑い話だった。柴先生はこの時も本当に嬉しそうに笑い、何度も「よかったね」と言いながらお酒を飲まれていた。
3. おわりに
今年の3月、柴先生の四十九日が過ぎた頃、奥様に無理を言ってご自宅にお邪魔し、お線香をあげさせていただいた。その際、2回目の評価受審時の報告書冊子を1部持参し、奥様に手渡した。柴先生が「本学での最後の仕事」と仰って残した物を奥様に是非ご覧になっていただきたいと思ったからだ。当時、こういう仲間たちとこんな仕事をしているのだと、奥様にも時々お話しになられていたそうである。
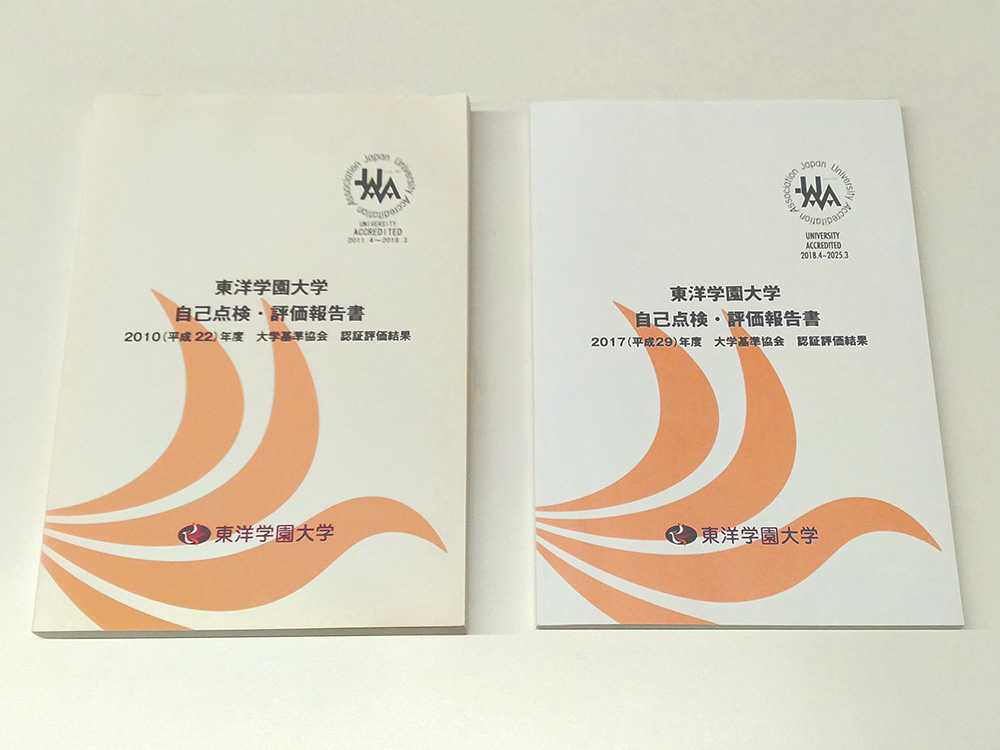
1回目と2回目の報告書冊子
何度も繰り返すが、この「認証評価」にまつわるコラムを書いてくれないかと頼まれた時、これは柴先生がお書きになるべきものだと真っ先に思った。原稿を書き終えようとしている今もそう思っている。私が書いた原稿を見て、先生は何と仰るだろうか。おそらく、柴先生が2回の認証評価作業の中で味わわれたご苦労や、大好きだった東洋学園大学を何があっても不適という評価にしてはならないという先生の想いは十分に表せていないだろう。だから、やはり柴先生に書いてほしかった。先生の想いがこもった原稿を読みたかった。
ゆったりとご退職後の生活をお過ごしになる中で、大好きだったお酒をチビリチビリとやりながら書いた原稿が、大好きだった煙草の香りとともに送られてくる。そんなことを想像した。
柴 鉄也先生のご冥福を心からお祈り申し上げる。