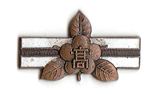2012年度「最後の旧制高校 東洋高等学校 ―教養教育への挑戦」
占領期に一瞬の光芒を放って消えた特設旧制高校の全容
公開 2012年5月28日~2013年3月29日
本年(2012年)は東洋学園大学が共学の四年制大学として1992(平成4)年4月、東洋女子短期大学流山キャンパスに併設の形で開学してから20周年となります。
四年制大学と短期大学の相違点は研究機関としての位置付けのほか、初級学年における一般教育科目(教養科目)の厚みの違いが挙げられます。
東洋学園の男女共学と本格的教養教育の開始は1992年とされていますが、戦後占領期の学制改革中にこの取り組みはすでになされ、成果を上げていたことは忘れ去られていました。
それが、東洋高等学校という旧制高等教育機関です。
旧制高等学校の萌芽として明治初期の東京大学予備門が挙げられますが、その後は幾多の制度上、また名称の変遷があり、政府、文部当局はこれを帝国大学とは別の、社会の中堅層を育成する専門教育機関に位置付けようと試みながら、実態は終始、帝国大学(等)への進学課程(予備教育)として機能しました。第一高等学校(現 東京大学)から始まる官立ナンバースクール、これに続く地名スクール、高等学校令(1918年改正)の理想を体現しようとした公私立七年制高校など旧制高校38校*は今日なお高い評価を得ており、専門課程である大学への原則無試験進学を保障された教養教育の場として、エリート教育の弊害を指摘されつつも近代学校教育の成功例と目す論調が主流です。
東洋高等学校は1947(昭和22)年から1950(昭和25)年の間、津田沼校舎に存在した理科乙類(医学部進学課程)の旧制高等学校でした。
同校は東京帝国大学出身の、あるいは大学院在学中の若手教員を主体に、主として自然科学分野の教養科目と、ドイツ語を第一外国語とし、英語、ラテン語、ギリシャ語の第二外国語が教授されました。
学生は学業のみならず、硬式野球部などの運動部はリーグ戦やインターハイに出場し、文化系団体は壁新聞や機関紙を定期的に発行し、寄宿舎「茜寮」の寮祭では「アルト・ハイデルベルク」を演出、上演し、夜は街頭ストームに興じました。
卒業生は1回生70名(男子61名・女子9名)のみながら、医学部・医科大学へ進学して医師となった者25名(うち大学教員2名)、歯科医師8名、薬剤師や理数科の学校教員、工学系大学教員や実業団野球選手など、多彩な人材を輩出しました。
旧制東洋高校に関する資料は皆無に近く、卒業生の消息も知れず、その存在さえ疑われましたが、昨年(2011年)、同窓会「ならしの会」の存続が分かりました。同会は1994年に記念誌『ならしの』を刊行し、歴史の闇に埋もれようとしていた旧制東洋高校をしっかりと歴史に刻んでいました。
旧学制の末期に、なぜ東洋学園に旧制高校が設置されたのか。旧制女子歯科医専から新制女子短期大学への移行期に、男女共学かつ医学部進学課程としての教養教育を行った理由は何か。
明治維新から戦後占領期の学制改革に至る高等教育の変遷を踏まえつつ、新制大学に必須とされた教養教育への「東洋学園の挑戦」を、写真と資料で解き明かします。
「東洋高校の再生」(記念誌『ならしの』)
元講師:茂手木元蔵(1912~1998 西洋古代中世哲学・西洋古典語)
"旧制東洋高校はいずれ「まぼろし」化するが、その理想は何らかの形で残し伝えられることを望む。その原動力は偏に卒業生諸君の、今はなき母校を愛し、各自の尊い青春を再評価する心の中にあると思う。"

旧制東洋高等学校襟章
(襟章クリックで本展ポスターが開きます)
*大学予科や戦後特設校を加えれば数字は異なりますが、今日「38校」が最も一般的な解釈。
※千代田区三崎町の東洋高等学校様(新制高校)とは無関係です。同校との混同を避けるため、展示、解説書では原則「旧制東洋高等学校(旧制東洋高校)」の表記を用います。