Academic Life & Research
教育・研究
現代史からひも解く中国料理の発展とは。特別講座「未来は共に創る」第7回
2023.11.08
本学では、一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講しています。
今年は一般聴講者を含む対面での講義が復活し、「未来は共に創る――アジア共同体の新しい地平線」という全体テーマのもと、アジアの諸問題に関する専門家や有識者を講師として招へい。
11/2(木)に開催された第7回は、講師として慶應義塾大学教授の岩間一弘氏にご登壇いただきました。

今回の講義テーマは「中国料理の現代史」。
東洋史・東アジア近現代史を専門とし、特に東アジアの近現代文化に深い知見を持つ岩間氏に、中国現代史と中国料理文化についてお話いただきました。

岩間氏
岩間氏はまず、2021年に中国の国家級無形文化遺産に登録された「螺蛳粉(タニシビーフン)」を例に、歴史の浅い料理(文化)であっても、その存在感が高まることで国内で無形文化遺産となり、国をあげてバックアップされていくという中国の文化保全について解説。
「中国・柳州の煮タニシやビーフンといった食文化が合わさって1980年代に流行した屋台料理が、インターネットを媒介とした販路拡大により中国国内で無形文化遺産となった」と紹介しました。
続いて、「中国料理の現代史とナショナリズム」をテーマに中国料理を概説。
「運河の発達により小麦の流通が盛んになった」「宋時代に炒める調理法が発達し、美味しく食べられるものが増えた」「明時代にトウモロコシ、サツマイモなど新しい作物が流通し、人口の急増につながった」など、中国の食文化に大きな影響を与えた歴史の転換点についてお話いただきました。
最後に、現代日本と中国料理の関係に言及した岩間氏。
「日本で発展した中国料理もあれば、韓国で発展した中国料理もある。中国以外の様々な国で『中国料理』が独自の進化を遂げている。日本では今、従来の『町中華』に加え、『ガチ中華』のジャンルも生まれており、ぜひ試してほしい」と述べ、講演を終えました。
質疑応答では、中国出身の本学の留学生から村の結婚式でふるまわれる中国料理の紹介や、日本で提供される中国料理の味付けへの違和感など、リアルな意見が。
岩間氏との活発な意見交換が行われました。
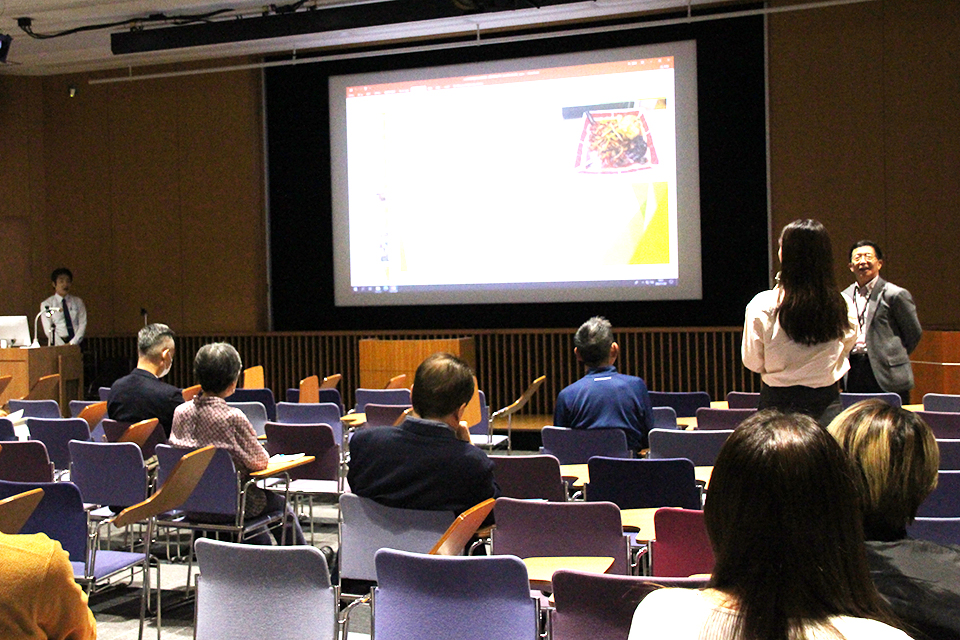
質疑応答の様子
