Academic Life & Research
教育・研究
フィクションの中で活躍する「役割語」とは。言語学者の金水敏氏がグロコミ学部でゲスト講義
2022.11.17
11/2(水)、グローバル・コミュニケーション学部の「言語学研究ゼミ」(依田悠介准教授)に、放送大学特任教授・大阪大学栄誉教授で言語学者の金水敏氏をゲスト講師として招聘。
「フィクションに現れる“役割語”について」をテーマに、話し手のキャラクターや性別、年齢など人物類型に従った話し方である「役割語」について、お話しいただきました。

「役割語」とは、話者の年齢や性別、職業など特定の人物像を想起させる言葉遣いを指し、金水氏がその概念を提唱しました。
たとえば、「わたしはその秘密を知っている」を「わしはその秘密を知っておるのじゃよ」と一人称や語尾を変換することで、受け手に話者の人物像を伝える表現手法です。
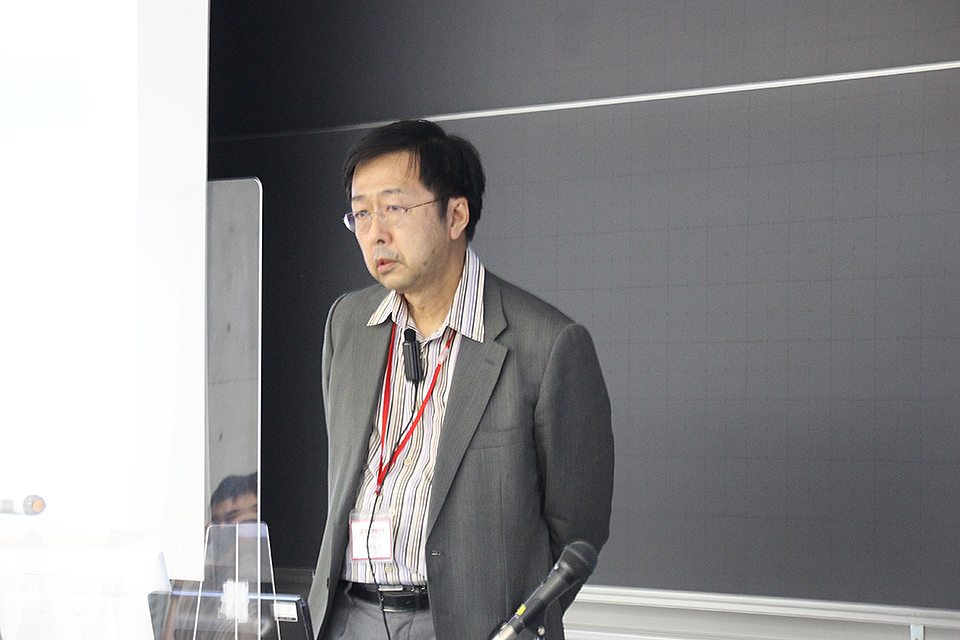
金水敏氏
金水氏は冒頭、「“すてきですわ”という言葉だけで、なぜ『話者は女性だ』と思うのか」と提起。
実際にそのような話し方をする人は少ないにも関わらず、話者のイメージが特定の人物像に結び付くのは、「幼少期に触れた絵本や漫画などを情報源とした、話し方のステレオタイプである」と解説しました。
次いで、日本の著名なアニメや映画の事例を交えながら、具体的に役割語を説明。
語尾を「だ」で言い切る・「わよ」「わね」とするなど、役割語を使うことで性差を表した例や、権力を示すためにあえて男性的な役割語を使う女性キャラクターなどを紹介しました。
また、作者が役割語を用いることで「そのキャラクターが劇中でどのような役割をもつか」を受け手に伝えようとする「巨視的コミュニケーション」についての解説も行われました。

さらに金水氏は、時代とともに変化してきた役割語についても言及。
一般的に男性が用いる「ぼく」や「おれ」という一人称の起源や、現在とは違った使われ方をしていたことに触れ、時代とともに少しずつ更新されていく役割語もあることをお話しいただきました。
最後に金水氏は、「役割語は現実の社会的グループの話し方に基づいて形成されたステレオタイプを起源とするが、時代とともに変化も見られる。今後、言語や社会など人文学の研究対象への新しい切り口となるのでは」と総括。
質疑応答では、「男女の差をなくそうとしている社会において、役割語の将来はどうなる?」「英語の役割語が日本語より少ないのはなぜか?」といった質問に、専門的な知見からお答えいただきました。
「言語学研究ゼミ」を担当する依田悠介准教授のコメント:
「日本語研究を牽引してきた研究者であり、また、役割語研究の第一人者である金水先生にいらしていただきお話を伺えたこと自体が本学にとっても大変貴重な機会でした。また、本学に金水先生をお招きできたことも大変光栄です。授業では近年のVTuberの『お嬢様ブーム』の話など学生に身近な話題を盛り込んだ“固くない”言語研究の醍醐味を生で味わえた良い機会であったと思います。今後、グローバル・コミュニケーションの学びとして、社会と言語のつながりについて卒業論文を執筆するにあたって学生たちにとってはたくさんの学びがあったのではないかと考えています。また、授業後には金水先生との交流の機会もあり、若者ことばの「知らんけど」の話などで盛り上がったりしていて、研究者が遠い世界の「博士」ではなく、身近なものであるということを学生たちは感じられたのではないかと思います」
