Academic Life & Research
教育・研究
埼玉県立越谷北高校新聞部が飯尾牧子教授を取材!若者の言葉遣いと言葉の変化に着目
2023.11.17
10/25(水)、英語コミュニケーション学科の飯尾牧子教授が埼玉県立越谷北高等学校新聞部の生徒より「若者言葉」について取材を受けました。

越谷北高校で11月発刊予定の校内タブロイド新聞に向けた取材の様子
越ケ谷北高等学校新聞部は、全国総合文化祭新聞部門に2002年度から19回連続出場。
さらに、埼玉県高等学校新聞コンクールでは2002年度から最優秀賞を18回受賞するなど、活発に活動しています。
埼玉県越谷北高等学校新聞部の活動はこちら
新聞部の生徒たちは、古文の授業を通して意味が変わってしまった言葉を知り、「言葉はなぜ変化したのか」といった疑問を持ったことで、大学生を中心とした若者のコミュニケーションや「えっと」「なんか」といった談話標識を研究する飯尾牧子教授にインタビューの依頼をしました。
10/25(水)に行われたインタビューでは、新聞部の生徒から「飯尾教授が大学生のキャンパス言葉や談話標識に着目した理由」「大学生での言葉を研究して感じること」といった質問が次々にあがったほか、「変化する言葉を正す(元に戻す)必要はないのか」という鋭い質問も。
飯尾教授は「変わることは悪いことではない。変わらないと言語は死んでしまう。若者(大学生など)がいろいろな言葉を生み出し、すぐに消える言葉もあれば、長く使われる言葉は辞書にのる。言葉は変化していくのが常」と生徒に伝えました。
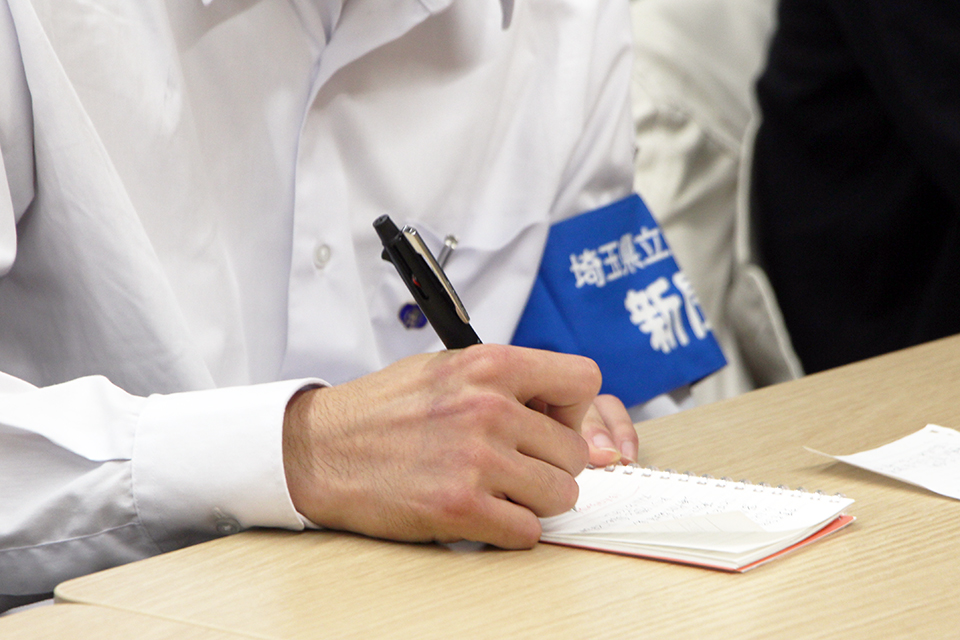
手書きでメモを取る新聞部の生徒たち
最初は緊張の面持ちだった新聞部の生徒たちも、飯尾教授に質問を重ねていく中で笑顔を浮かべるなど、インタビューは徐々に和やかな雰囲気に。
生徒たちが当たり前に使っていた「ら抜き言葉」も、昔は間違いとされていたことを飯尾教授から聞いた時には、驚きを隠せない様子でした。

左から1年生2人と2年生
最後に、新聞部の生徒たちから越谷北校生へのメッセージを求められた飯尾教授は、「何気ない言葉に興味を持ち、変化していることを感じてほしい」と今回の取材のテーマに触れ、「日本はグローバル社会となり、英語は必須のツールになる。自分とは違う文化を持つ人との『異文化コミュニケーション』を国内外の方関わらず行って、人に興味の持てる人になってほしい」と話しました。

今回の取材は、新聞部の生徒たちが記事としてまとめ、越谷北高等学校の校内で発刊されるタブロイド新聞で紹介される予定です。
越谷北高校新聞部の皆さん、発刊を楽しみにしています!
