Academic Life & Research
教育・研究
「誰一人取り残さない」をテーマに、国内外の社会問題を独自視点で研究。玉井ゼミの卒論発表会
2022.01.06
12/22(水)、グローバル・コミュニケーション学科の「フィールド文化研究ゼミ」(玉井隆専任講師)の4年生が卒業論文発表会を実施。
同ゼミではSDGsの「誰一人取り残さない」という理念を全体テーマに、幅広い角度から各学生が独自の研究を行っており、今回は「教育・ケア・家族・子ども」「美・音楽・身体」「with コロナの世界」という3部構成で計11名が登壇。
3年ゼミ・2年ゼミに所属する学生も参加し、質疑応答が行われました。

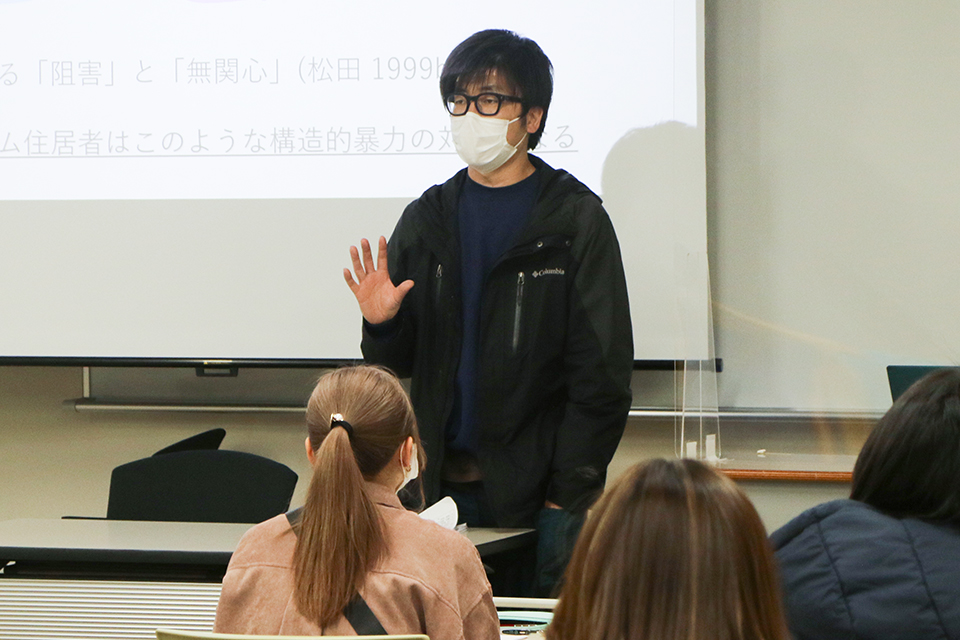
玉井隆専任講師
「教育・ケア・家族・子ども」パートには3名が登壇。
日本における教育格差の広がりに着目し世界4カ国の学外教育(塾やホームスクーリングなど)を調査した研究を皮切りに、核家族化による家庭内エッセンシャルケアワーカーの孤立問題とそれを補完するコミュニティの必要性についての考察、フィリピンのストリートチルドレン問題について社会背景・家庭背景・労働問題・現状の支援策を分析し、継続的な支援による貧困問題へのアプローチ提言と、子どもや家庭、社会が抱える問題に対し三者三様の視点での研究が発表されました。

「美・音楽・身体」パートは3名の学生が登壇しました。
「化粧」文化の歴史とトレンドの推移について研究した学生に続き、主に女性の身体美に対する多様性を訴える “ボディ・ポジティブ”ムーブメントについて、それぞれ別の角度から研究した2名の発表が行われました。

最後は「with コロナの世界」パート。
まずは函館のストリートダンスシーンでフィールド調査を行い、コミュニティにおける独自のルールとコロナ禍におけるダンス文化の動向に焦点を当てた研究成果が報告されました。
次に中国出身の学生が、中国・武漢市の医療崩壊と仮設病院の設営、中国政府による防疫・健康情報管理システムの施行など、新型コロナウイルス感染症を機に起きた急激な社会変容について発表しました。
続いて、南カリフォルニアの社会構造におけるアフリカ系アメリカ人に対する制度的差別について研究する学生が登壇し、自身でインタビューを行った現場の声を紹介しました。
卒論発表会のラストを担当したのは、ケニア最大のスラムにおけるコロナ禍対応について研究した学生。
コロナ対策から派生した警察の暴力や政府の都市計画による学校の破壊といった、スラム排除に向けた動きと、それに対抗する形で発生している地域住民の相互扶助の現状という、「誰一人取り残さない」という全体テーマを実直に反映した研究で発表会を締めくくりました。

研究対象も視点も幅広い発表が続く中、質疑応答では4年生同士によるお互いの研究に対する活発な意見交換が行われ、さらに聴衆として参加した2、3年生も質疑応答に積極的に参加。
細かくメモを取りながら発表を聞く学生も多く、自分の研究に活かそうとする真剣な姿が見られました。

東洋学園大学では、各ゼミで今回のような卒業論文発表会が行われており、1月末には教員・ゼミの推薦学生による学部別の発表会も実施予定です。
