Academic Life & Research
教育・研究
特別講座「アジア共同体の新しい視角」第14回報告:世界経済の動向とアジアの役割
2022.01.14
一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。1/7(金)に行われた第14回(最終回)では、元国連大使で桜美林大学アジア・ユーラシア総合研究所代表理事を務める谷口誠氏にお話を伺いました。

谷口誠氏
谷口氏は1959年に外務省に入省。日本人として2人目のユニセフ議長、国連大使、岩手県立大学学長等を歴任され、現在は新渡戸国際塾の塾長として次世代の人材育成に務められています。
冒頭、谷口氏は世界を席巻するコロナ禍について、「ウイルスに対して共に戦うのではなく、むしろ世界が分断されていることに危機感を覚える」と、今回の講義のテーマに通じる問題意識に言及。
かつて大使を務めたパプアニューギニアのマラリアを例に挙げ、「新薬が開発されWHOが撲滅を宣言したあとも、蚊による媒介が依然人々を苦しめている」と述べ、「コロナも医学が進んでいる先進国で感染数が圧倒的に多いのは人間の驕りのせいでは」と警鐘を鳴らし、武漢の研究所で当初、中国とアメリカの研究者が共に研究したことを挙げつつ「国際的な協力が最も大切である」と語りました。
次いで日本に話題を転じ、ノーベル医学賞を選ぶスウェーデンの研究所を訪問した際に、日本からは資金が拠出されていないことを知り、当時の日本に国際的な視野が欠け、短期的な発想による国際協力が行われていたことに言及。
さらに、岩手県立大学時代に文科省から研究費を得るためには3年単位で成果を出すことが求められたというご経験を挙げつつ、日本の国際協力や教育政策の問題点について語りました。
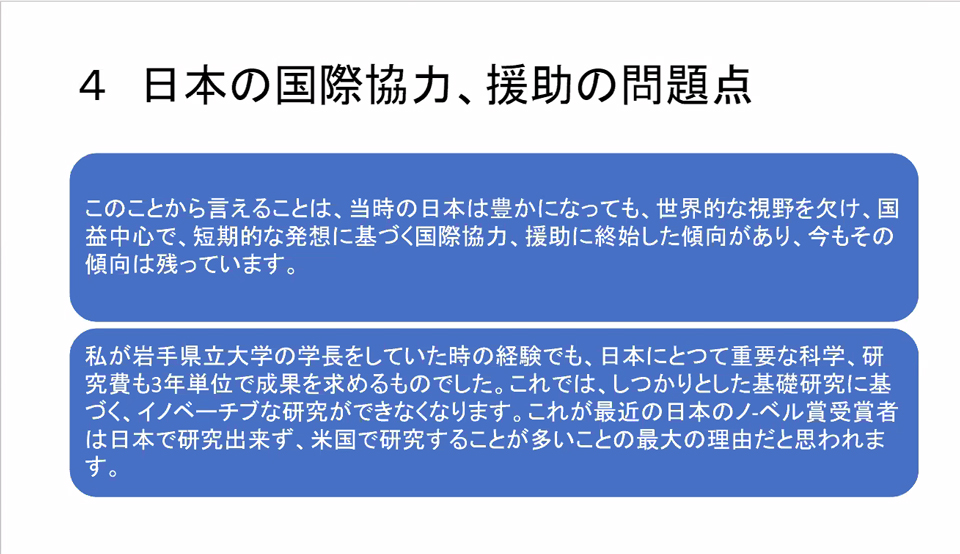
本題である東アジアについてのお話では、まず、谷口氏も勤めていた国際機関、経済協力開発機構(OECD)の予測データについて解説。
同機構では2060年にはアジアが大躍進すると予測しているそうで、GNP第1位は中国、2位はアメリカ、3位はインド、2060年を過ぎると15億の人口を抱えるインドが1位、2位が中国、3位がインドネシアとなり、世界のGDPの半分をアジアが占めると言われています。
しかしながら、谷口氏はかつて著書で「2010~15年の間に中国は日本を追い抜く」と予想しており、今回の講義でも日本は2040年には人口が1億人を割ることに触れつつ、「日本がアジアのリーダーからアジアの一国となるのは避けられない」と述べられました。
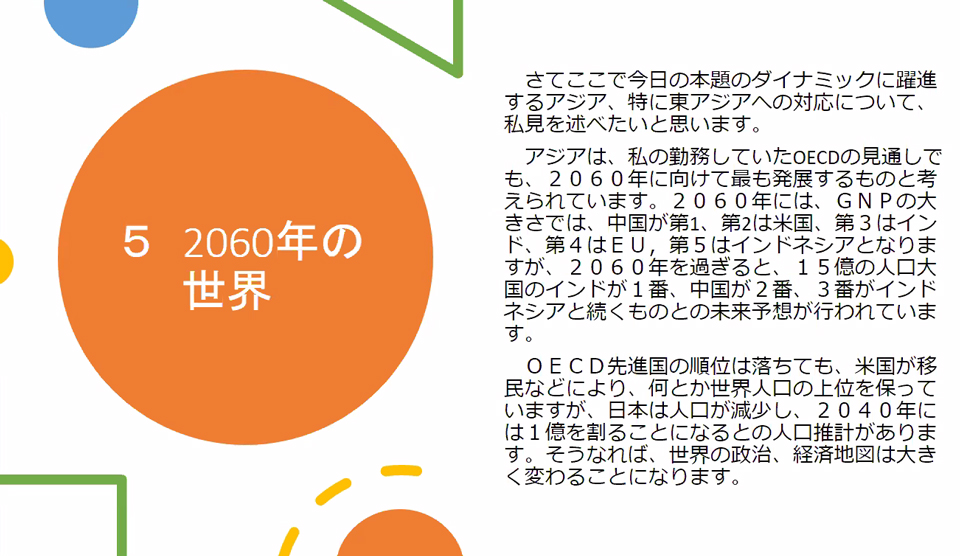
そのような状況において日本は今後どう対応すべきなのか、谷口氏は「中国が一帯一路政策のために提唱し主導するAIIB(アジアインフラ投資銀行)に日本も参加すべきである」と提言しました。
日本が参加する「TPP(環太平洋パートナーシップ)」からはアメリカが離脱、「自由で開かれたインド太平洋戦略」に関しては、インドは中国が最大の貿易国であることから、したたかな外交戦略を展開し、中国包囲網に同調することはないだろうと分析。
「アメリカ一辺倒では日本は行き詰まる。軸足をアジアに移して多角的な外交を進めるべきである」「日本も科学や教育の高い水準を持つ人材を育成していけば、少ない人口ながら存在感をもつEUなどのMIDDLE POWERと同様に、成長することが可能である」と、その展望を示しました。
また、中国・韓国と経済関係を強化し、「東アジア共同体」を形成し、信頼関係を醸成することが最大の課題であると述べて、講座を締めくくりました。
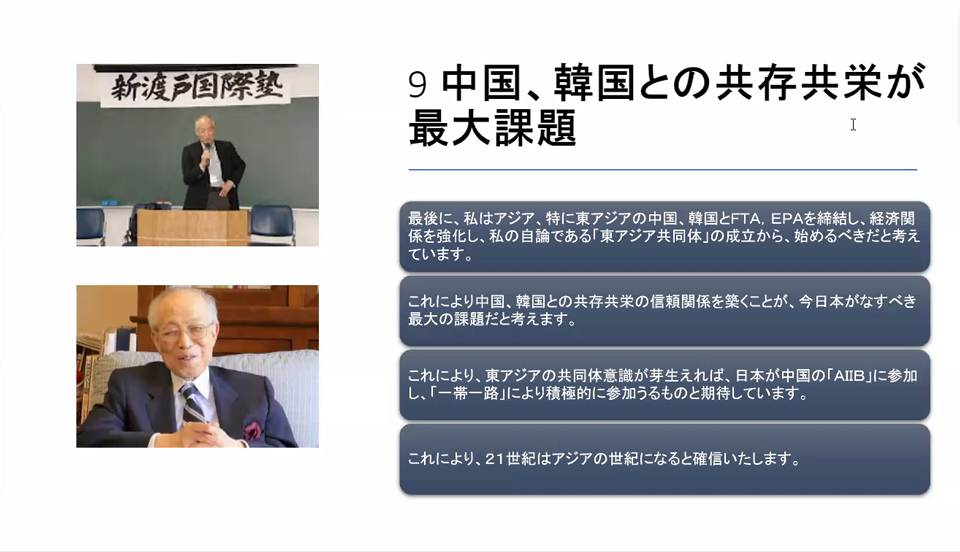
今年度の特別講座「アジア共同体の新しい視角」は今回の講義をもって全14回を終了。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。
