Academic Life & Research
教育・研究
愛読書から始皇帝の実像に迫る。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第12回目を開講
2022.12.16
世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。
12/12(月)、第12回「始皇帝の愛読書」を開講しました。
本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。
第12回の講師は学習院大学名誉教授・鶴間和幸氏。
鶴間氏は東京大学大学院博士課程で学んだ後、茨城大学教授、学習院大学教授を経て現職に就かれました。
始皇帝研究の第一人者として、兵馬俑展「兵馬俑と古代中国」等で監修を行うなど幅広く活躍されています。
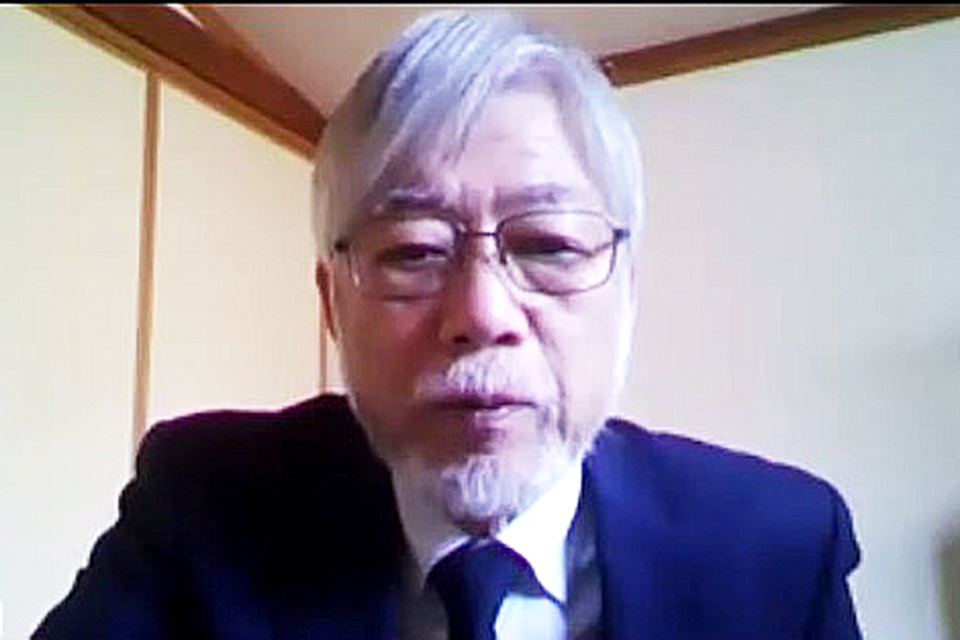
鶴間和幸氏
鶴間氏は講座の冒頭で、13歳の若さで即位し、中国で初めて天下統一を果たした秦の始皇帝が多様な書籍を愛読していたことを紹介。「愛読書という新たな視点で始皇帝50年の生涯を4つの時代に分けてたどりたい」と述べました。
まずは10代の始皇帝が帝王学を学んだとされる李斯と韓非について紹介。
李斯が短文で「なぜ始皇帝の祖先・覇者穆公は東方の六国を併合できなかったのか」を問いかけ、始皇帝に考えさせたというエピソードを紹介しました。
また、始皇帝が「(韓非に)会えれば死んでも悔いはない」とまで言って愛読したという『韓非子』について、「亡国を人間の死にたとえるなど、韓非の憂いと訴えに満ちた文章が始皇帝の心にも響いたのでは」と分析しました。
次に始皇帝が20代の頃の愛読書として、大商人であり後に秦の宰相として権勢を振るった呂不韋が天地・万物・古今の事績をまとめた『呂氏春秋』について紹介。
特に、『呂氏春秋』のなかでも、季節を12か月の時令に分け、それぞれの季節に天子が務める事項が記された『十二紀』について取り上げ、「秋が刑罰と殺戮を行う月であることや、戦争の詳細な方法なども記されており、始皇帝の政治へ影響を与えたのでは」との見解を述べました。
その理由として、司馬遷の書に書かれた“始皇帝が40代前半に『十二紀』の教えを実践に移し、天下統一へ歩みを進めた”というエピソードを紹介。
同書によると、始皇帝は『十二紀』に従って自らが統一した地方を5回にわたって巡行し、顕彰文を2つの石に刻んだといわれていますが、これについて鶴間氏は「臣下が始皇帝の功績を後世に伝えるためのメッセージだったのではないか」と考察しました。

最後に、50歳で亡くなった始皇帝の晩年について、再び『十二紀』を取り上げながら解説。
始皇帝の陵墓について、「始皇帝は『十二紀』の「節喪」章に学び、生前より70万人を動員して“盗掘されず、水に沈まぬよう三層の地下水脈まで掘り下げた”陵墓を造営した」と紹介しました。
二重の城壁に囲まれた壮観な陵墓は『十二紀』の記述に一致することから、鶴間氏は「呂不韋が与えた帝王学実践の知識はのちに確実に実行された」と述べ、愛読した書籍に影響を受けた始皇帝の生涯を総括して講座を終了しました。
質疑応答では、日本書紀に記された始皇帝に関する記述など、さまざまな角度から質問が寄せられ、斬新な研究の視点に立って回答されました。
今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。
一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。
次回は12/19(月)、「人づくりは先人に学ぶ――東洋思想・江戸商人の智慧 」というテーマで、中央カレッジ代表・中島利郎氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。
