Academic Life & Research
教育・研究
鹿鳴館を描いた3つの文学作品から読み解く、日本近代化の本質とは。特別講座「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」第7回
2024.11.15
本学では、一般財団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講しています。
今年は「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」という全体テーマのもと、アジアの諸問題に関する専門家や有識者を講師として招へい。
全15回のオムニバス形式で講義を行います。
10/31(木)に開催された第7回は、講師として元東洋学園大学教授の神田由美子氏にご登壇いただきました。
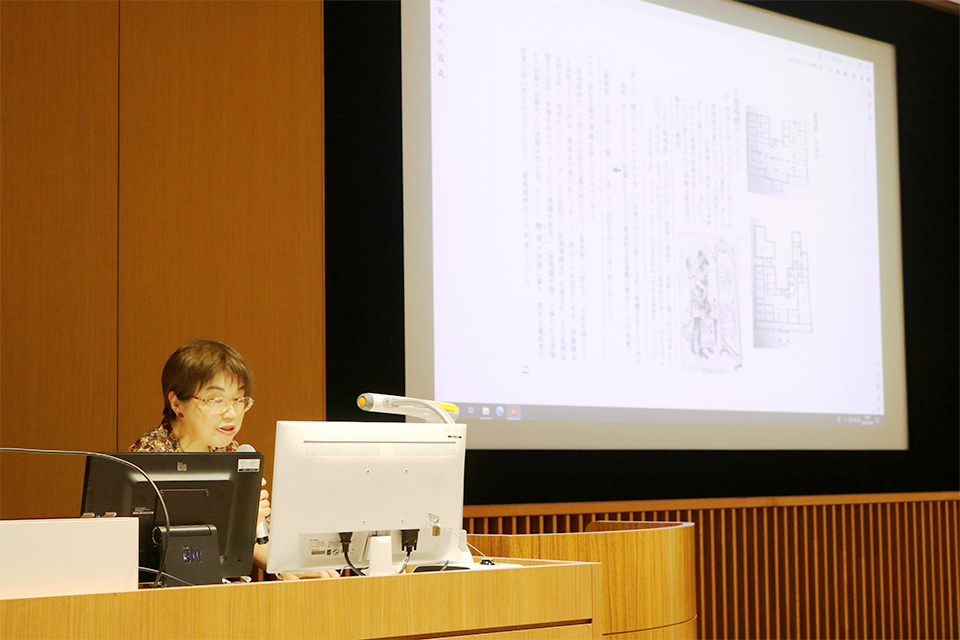
今回の講義テーマは「東京を舞台とした文学作品から、日本の近代化の本質を探る」。
日本近現代文学と東京との関係を探求してきた神田氏に、「鹿鳴館」を題材に3人の近代作家たちが描いた文学を通じて日本の近代化を見るとき、現代の我々にどのような示唆があるのか解説していただきました。
講義冒頭、神田氏は日本の近代化は、鎖国時代を経て西洋諸国から200年遅れをとったため、西洋の模倣をすることから始まったと言及。
その象徴でもある「鹿鳴館」について、成り立ちや歴史的背景を、当時の風評を交えながら解説しました。
続いて、「鹿鳴館」が実在した時代に小説を書いた泉鏡花、追憶としての「鹿鳴館」を描いた芥川龍之介、敗戦の結果、日本近代化の失敗を目の当たりにし、「鹿鳴館」という近代化の始まりを回顧した三島由紀夫を紹介。
年代の違う3人と「鹿鳴館」の関係性について、年表を用いて時間軸に沿って説明しました。

神田氏

講義後半は、泉鏡花の小説『貧民倶楽部』、芥川龍之介の小説『舞踏会』、三島由紀夫の戯曲『鹿鳴館』について、それぞれのあらすじ、主題、影響について語った神田氏。
「明治」「大正」「昭和」と時代を超えて描かれる「鹿鳴館」をめぐる文学には、「欧米に比べて自らは後進国だと考える日本が辿らざるを得なかった急激な近代化の歪みと憧れが描かれている」としました。
さらに「議会制度や鉄道、学校など目に見える部分は欧米化できても、近代社会の根本を支える個人の自由や人権を伴っていなかったことに『鹿鳴館』から続くアジア的な悲哀を今も生んでいる」と述べて、講義を終えました。
講義終了後には質疑応答の時間が行われ、「鹿鳴館は近代化にプラスになったのか、マイナスだったのか」「(講師が)小説にどうやって出会っているのか」「鹿鳴館を始め、歴史的建造物が無くなっていることをどう思うか」といった質問があがり、それぞれ丁寧な回答をいただきました。
さらに、「小説を読むことで時や場所を超えて世界の中へ入ることができる。それを楽しみながら、小説の優れた構成力に触れることができ、自然と学力がつくので、ぜひ小説を読んでほしい」とアドバイスをいただきました。
同講座は本学学生が履修するほか、一般の方も受講可能な公開講座として開講されています。
各回の講師・テーマ、聴講のお申し込み方法は以下ページよりご確認いただけます。
一般財団法人ユーラシア財団 from Asia 助成 特別講座
https://www.tyg.jp/koukaikouza/oneasia/index.html
