Academic Life & Research
教育・研究
私たちは今後どのような社会を目指すべきか?のヒントを探る。「SDGsフォーラム」開催報告
2021.11.08
10/17(日)、オンライン学園祭の同日開催企画として、本学SDGs教育プログラム開発研究プロジェクト主催の「SDGsフォーラム」を開催しました。
今回のテーマは、「SDGsと脱炭素社会の未来 ~人類の明るい持続可能な社会構築は可能か~」。
脱炭素社会を念頭に、私たちは今後どのような社会を目指すべきか?のヒントを探るべく、本学の教員陣に加えて3名の有識者をパネリストとして招聘し、オンライン上でご講演いただきました。
参加者は130名を超え、在学生のみならず社会人の方々にも多数ご参加いただき、本学の SDGs 教育への取り組みを外部に発信する好機にもなりました。

パネリスト1人目は、デンマークからご登壇いただいたCultural Translatorのニールセン朋子氏。
デンマーク在住歴20年であり、現地のSDGs事情にも精通しています。
講演では、「世界一幸福な環境先進国」ともいわれるデンマークで、どのようなSDGs教育が行われているのか?デンマークの企業や人々は、なぜSDGsに対して前向きなのか?といったことを、具体例や体験談を交えながらわかりやすく解説していただきました。
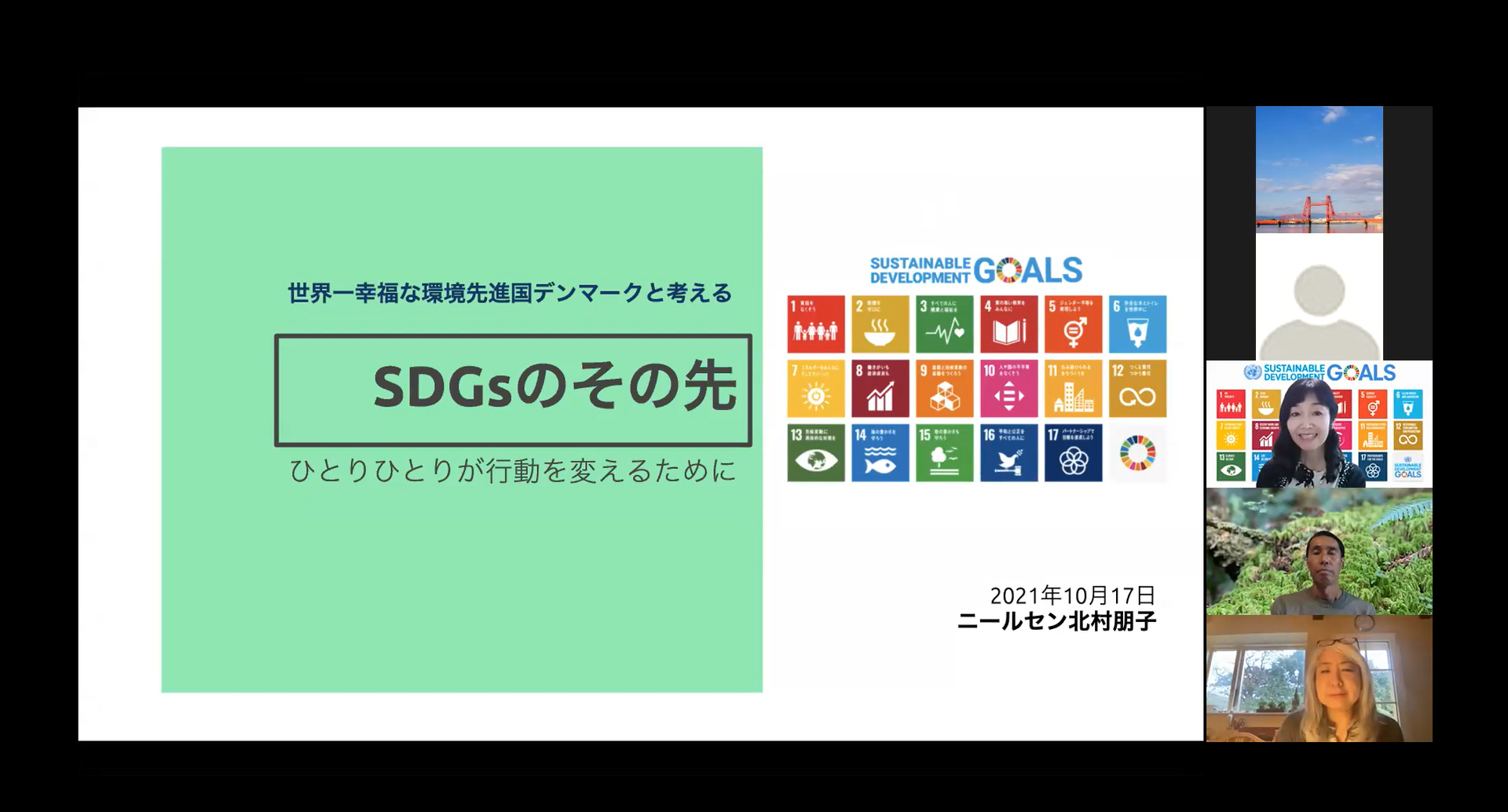
ニールセン氏による講演の様子
パネリスト2人目は、共同通信社編集委員の井田徹治氏。
これまで30年以上にわたって世界を飛び回り、環境問題を取材してきた経歴の持ち主です。講演では、世界各地で撮影した写真をもとに、温暖化による海面上昇、森林減少、土地劣化、プラスチックごみ汚染といった環境問題について解説。そして、「まずは自然を守ったうえで、経済や社会が成り立つというのがSDGsの根本。脱炭素だけでなく、根本的な変革が求められている」と提言されました。
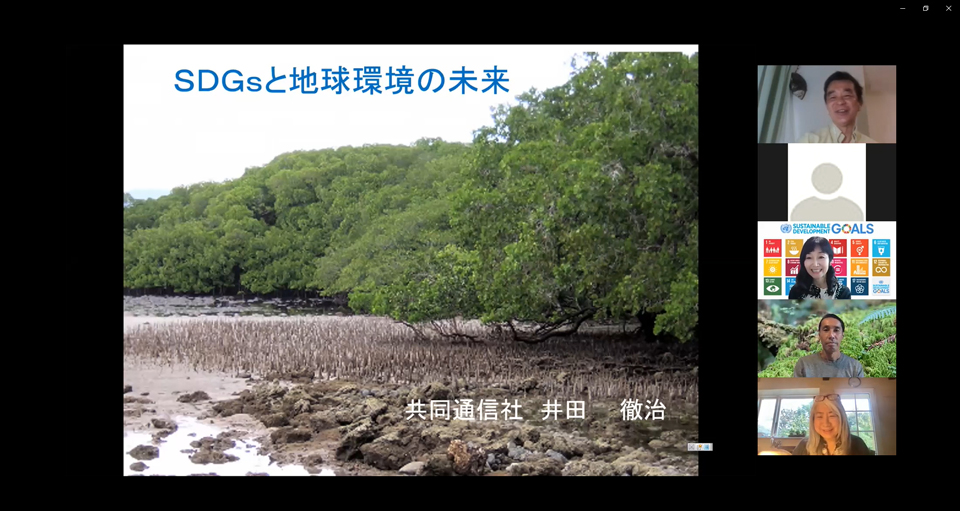
共同通信社の井田氏は、世界各地で撮影した写真を表示しながら講演
パネリスト3人目は、ソーシャルビジネスコンサルタント/社会活動家の辻井隆行氏。
海外の秘境を旅し、自然とふれあう中で、「先進国の私たちが便利を追い求めた結果、辺境の自然を破壊している」と気づき、環境問題への関心を深めたそうです。
講演では、気候変動などの環境問題に対する具体的な解決策を挙げつつ、結論として「人間が『分相応』に経済活動を行うことがサステナビリティにつながる」との意見を語っていただきました。
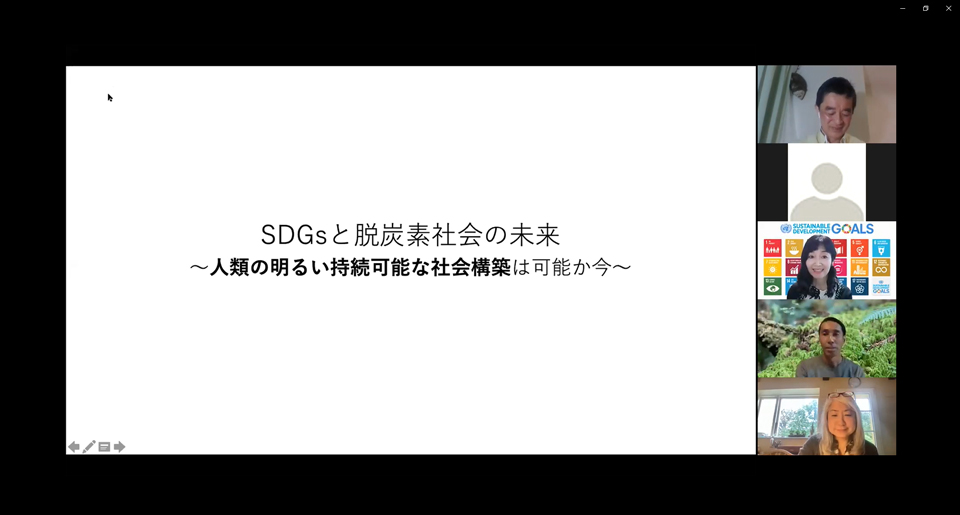
元パタゴニア日本支社長でもあり、環境問題に精通した辻井氏による講演の様子
講演後には参加者からたくさんの質問が寄せられ、活発な質疑応答が行われました。
SDGsの有識者である3名のお話は、多くの参加者にとってSDGsを「自分ごと」として捉えるきっかけになったようです。
これまでに開催されたSDGsフォーラムについてはこちら
コロナ禍がSDGsにもたらした影響を3つの視点から解説するウェビナー、国内外から約100名が参加
「SDGs時代のキャリア形成」について考えるオンラインフォーラムを開催
