Academic Life & Research
教育・研究
「太平洋をはさんだ隣国」ペルーと日本の関わりとは。特別講座「アジアに平和と相互理解を」第7回目を開講
2022.11.09
世界とアジアの新動向に焦点を当てた一般社団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座。
11/7(月)、第7回「遙かなる隣国南米ペルー:アジアとの戦略的パートナーシップ」を開講しました。
本講座は本学の授業科目を一般公開しているもので、8年目を迎えた2022年度は「アジアに平和と相互理解を――アジア共同体の基礎を固めるために」をテーマに、15回の講義(オンライン)を予定しています。
第7回の講師は駐ペルー日本大使・片山和之氏。
片山氏は京都大学卒業後、外務省に入省。
在中国日本国大使館を皮切りにアメリカ、マレーシア、ベルギー等で外交官のキャリアを積み、2020年より駐ペルー特命全権大使を務めています。

片山和之氏
片山氏は冒頭、今日は個人の立場による発言と断ったうえで、日本とペルーが1万5千キロ離れているものの、「太平洋をはさんだ隣国」であるという視点から、「ペルーへの理解を深め、日本とペルーとの関係の重要性に着目してもらいたい」と講座の趣旨を述べました。
そのうえでペルーの基本的知識を紹介。
公用語や国土面積、人口のほか、首都リマは南米で唯一太平洋に面している首都であることに触れました。
また、高度な文明を誇ったインカ帝国滅亡後、スペインの植民地を経て独立を果たした歴史、マチュピチュやナスカなど多様な観光資源にも言及。
政治体制については、日系初のフジモリ元大統領のもと国家崩壊寸前の治安や経済を立て直し、90年代には憲法が制定され、その体制が現在まで継続していると述べました。
経済においては、GDPはラテンアメリカ諸国中6番目であり、貿易相手国としては中国を筆頭に米国、ブラジルに次いで日本は第4位というデータを紹介しました。
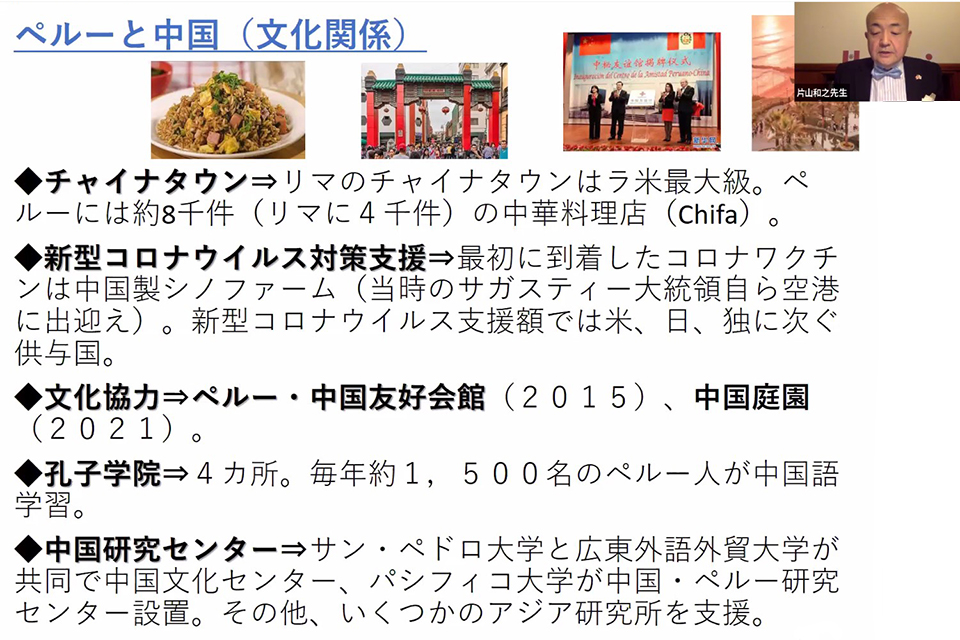
次いで、ペルーにおける中国のプレゼンスについて考察。
政治・経済の両面からその関係性を解説し、中南米諸国において中国の存在感が増す現状に対して「ペルーは中国の債務の罠には陥っておらず、その政治的影響力については限界があり、中国とは一定の距離を持った実利的関係にある」との見解を述べました。
そのような背景をふまえ、日本とペルーがなぜ「太平洋をはさんだ隣国」なのかという本題へ。
日本はペルーと1873年に外交関係を樹立、1899年から日本人の移住が開始され、現在ではブラジル、米国に次ぐ10万人規模の日系人社会が存在しています。
また、貿易においては、日本に銅鉱石など資源や農水産物を輸出、日本からは主に自動車を輸入するなど互いに重要な貿易相手国であり、太平洋をはさんだ結びつきを説明しました。
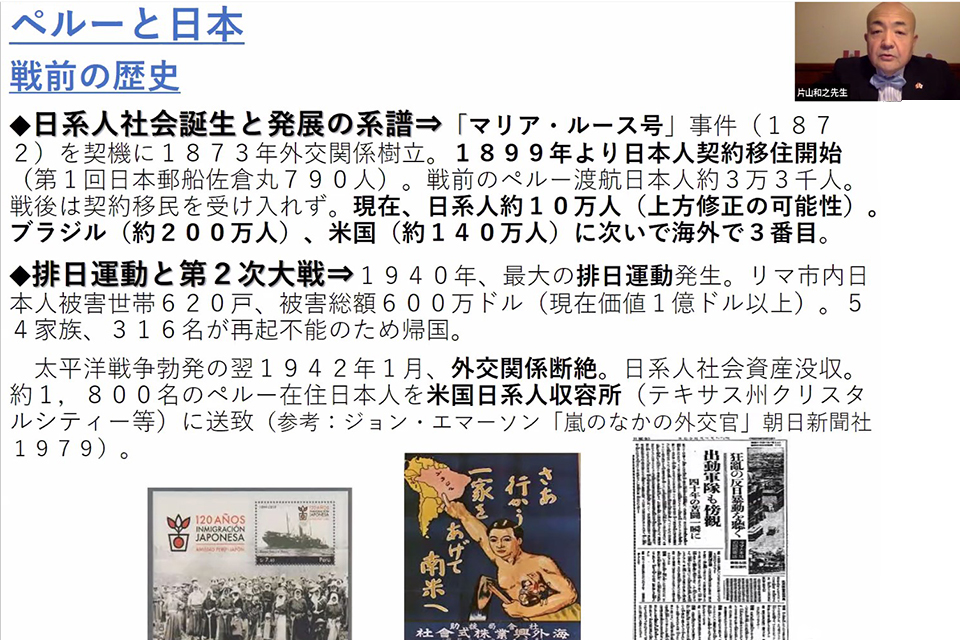
しかし、政治・経済・文化の面で両国の関係が深いにもかかわらず、日本のペルーに対する理解や関心が低いことから、片山氏は改めて「経済パートナー」「普遍的価値の共有」「高い対日好感度」「太平洋国家」などペルーの重要性を指摘。
「来年の外交樹立150周年を契機にペルーへの関心が拡大してほしい」との思いを受講者に伝え、講座を終了しました。
質疑応答では観光から経済、政治、日・米・中とペルーとの関係など、多岐にわたる質問が寄せられ、大使としての活動の紹介も含めて回答されました。
今年度は2023年1月まで全15回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。
一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。
次回は11/14(月)、「日中戦争の結末――外交の正否に関する再検討 」というテーマで、大東文化大学教授・鹿錫俊氏が講演します。ぜひ奮ってご参加ください。
