Academic Life & Research
教育・研究
中国電気自動車戦略と日本の自動車産業の展望。特別講座「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」第10回
2025.01.08
本学では、一般財団法人ユーラシア財団from Asia助成による特別講座を開講しています。
今年は「未曽有の大変局のなかでアジア共同体の未来を語る」という全体テーマのもと、アジアの諸問題に関する専門家や有識者を講師として招へい。
全15回のオムニバス形式で講義を行います。
11/21(木)に開催された第10回は、講師として長岡技術科学大学大学院教授の李志東氏にご登壇いただきました。
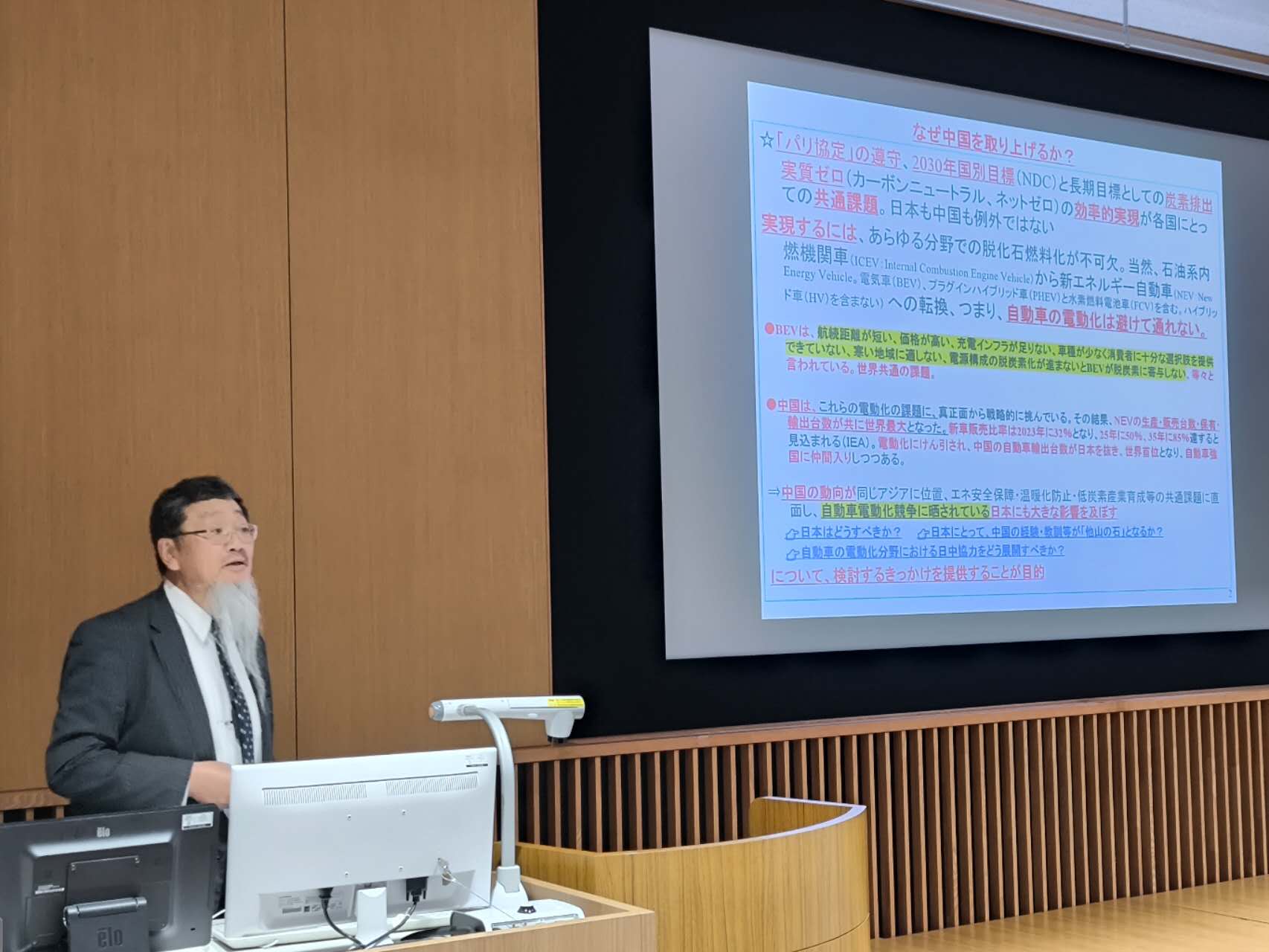
今回の講義テーマは「自動車電動化に向けた中国の取組みと国際社会への示唆」。
李氏は、日本政府、中国政府関連のエネルギー研究機関で長年研究を続け、近年は日本における中国の「NEV」(New energy vehicles/新エネルギー自動車)研究の第一人者として知られています。
講義では、中国が世界的なEV大国となった背景を中国独自の戦略から解説し、現在の国際的な影響力について、日本の自動車産業の展望とともにお話しいただきました。
講義冒頭、李氏は電気自動車産業を考察するにあたり、なぜ中国を取り上げるのかについて言及。
「かつて自動車強国であった日本を復活させるためにどうすれば良いのかをこの講義で考えていきたい」と語りました。
まず、NEVは中国の国家戦略であり、「石油安全保障問題」と「大気汚染問題」を解決する脱炭素化には自動車の電動化が必要不可欠であることから始まったと解説。
「中国が2009年に世界最大の自動車生産国になっても、電動化に関する認知度や普及という点では日本やドイツに遅れを取っており、自動車強国を目指すためにNEVの開発と普及に力を入れた」としました。
その手段として補助金制度や充電インフラを整備する取り組みは、中国の実情と合致し、農村部にまでNEVが普及したそうで、李氏は具体的な数値を示しながら、中国のEV産業の現状と今後の展望について語りました。
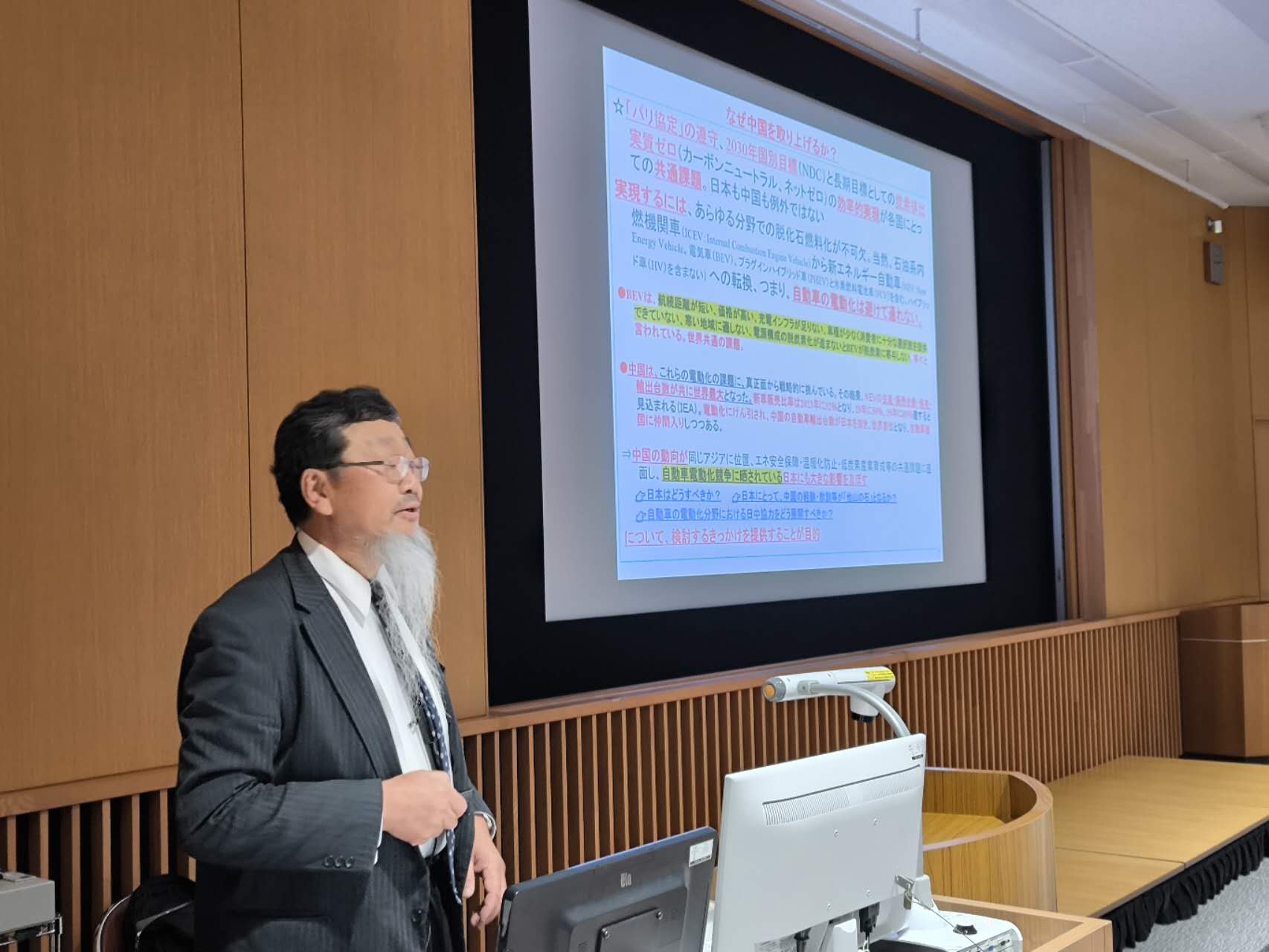
李氏
講義後半、日本が電気自動車分野において、中国に遅れを取ったことを認めた記事を紹介し、「認めたことが第一歩であり、ここからどうやって日本の自動車産業を復活させるのかを考えるべき」と語った李氏。
使用済み車載電池の適正処理など、今後の課題についても言及し、国際的に共通課題を解決するため相互協力が望まれると考察しました。
最後に、「『中国一強』ではなく、日本をはじめとする各国が中国と連携することで、日本の自動車産業の再生も可能」(李氏)との見解を述べ、講義を終えました。
講義終了後には質疑応答の時間が設けられ、「中国自動車の強みは?」「日本でも開発が進むペロブスカイト太陽発電を使ったEV車発展の可能性は?」といった質問が。
「日本が電気自動車産業において、こんなにも出遅れた一番の原因は?」という、核心をついた質問にも丁寧な回答をいただきました。
同講座は本学学生が履修するほか、一般の方も受講可能な公開講座として開講されています。
各回の講師・テーマ、聴講のお申し込み方法は以下ページよりご確認いただけます。
