Academic Life & Research
教育・研究
特別講座「ポストコロナの世界とアジア」第9回報告:世界の食料問題を学ぶ。中国の新型コロナ対策の現状も
2020.11.30
一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「ポストコロナの世界とアジア―アジア共同体への新しい可能性」第9回講座を11/20(金)に開催。
「世界の食料事情と中国ファクター」というテーマで、農林中金研究所理事研究員の阮蔚氏にご講演いただきました。
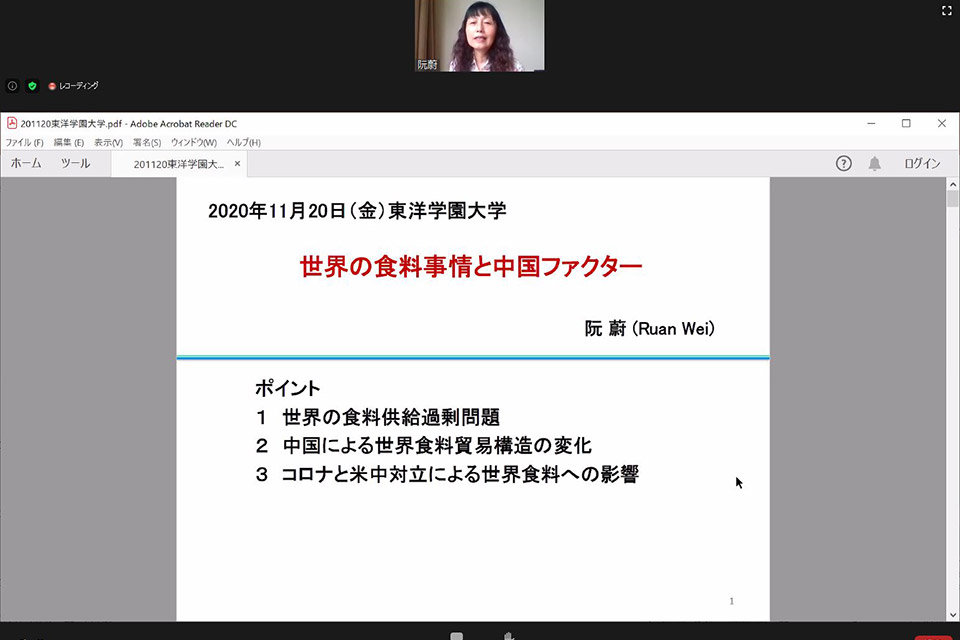

農林中金研究所 理事研究員の阮蔚氏
今回は何と、講師が滞在している中国・広州、しかも入国者向けの新型コロナウイルス感染症対策用一時宿泊施設からリアルタイムでのリモート講義を行うことに。
本題に入る前に、新型コロナウイルス感染症に対する日中の出入国管理体制についてお話しいただきました。
出国前・入国時のPCR検査や空港の検疫・税関や乗務スタッフが全員防護服という飛行機内の様子、ホテルで2週間の一時滞在とアプリを使った経過観察と証明書の発行・携帯義務など、中国の新型コロナウイルス感染症対策の現状について、大変貴重なお話を伺うことができました。
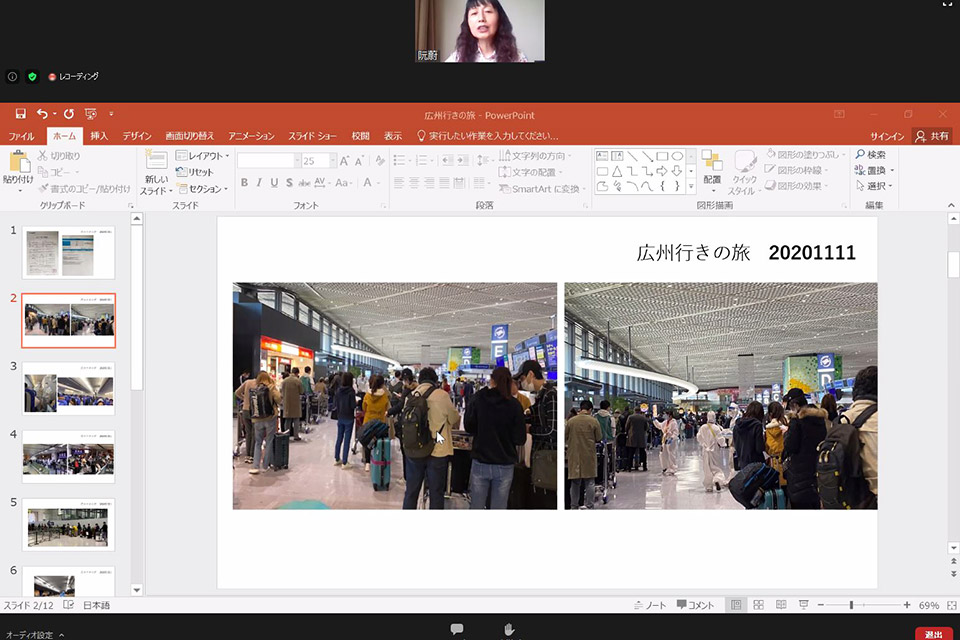
PCR検査の結果確認で大混雑の羽田空港。防護服姿のスタッフも。
その後、本題である「世界の食料事情と中国ファクター」についての講義がスタート。
現在、全世界的に見れば食料供給は過剰で、貧困の原因ではないそうです。
その中でも今回は、特に中国における「主食」の変化が大豆や豚肉といった世界の食料貿易にどのような影響を及ぼしているのかについてお話しいただきました。

コメはアジアの主食なので、貿易商品ではなく自給自足が中心となっている一方、大豆や豚肉については、世界全体の輸出量は多くないものの、中国での消費量が増大し、輸入需要が増えることで世界中の輸入価格が上がっているそうです。
食料品の輸出大国であるアメリカに対して、米中関係の悪化によって大豆はブラジル、トウモロコシはウクライナの輸出が急増していることなど、世界最大の人口である中国の動向が世界貿易に与える影響の大きさを分かりやすく解説していただきました。
質疑応答では新型コロナウイルス感染症の影響についての話題となり、農業と地球環境の関係が再認識され、身近な供給チェーンや「地産地消」が見直されている中で、日本の農業が注目されているというお話も。
品質が高く生産者の顔が見える日本の農産物は品質が良く、味だけでなく安全性も高いため、中国消費者の関心が高く日本の農村、加工場から直接買いたい、というニーズが生まれていることをお話しいただきました。
本講座は2021/1/8(金)まで、1/1(金)を除く毎週金曜日の13:00~14:30にZoomウェビナーによるオンライン講座として開講。
一般の方々は無料で受講可能ですので、以下URLより事前登録の上、ふるってご参加ください。
