Academic Life & Research
教育・研究
特別講座「アジア共同体の新しい視角」第4回報告:元中国大使の視点から語る日中関係
2021.10.11
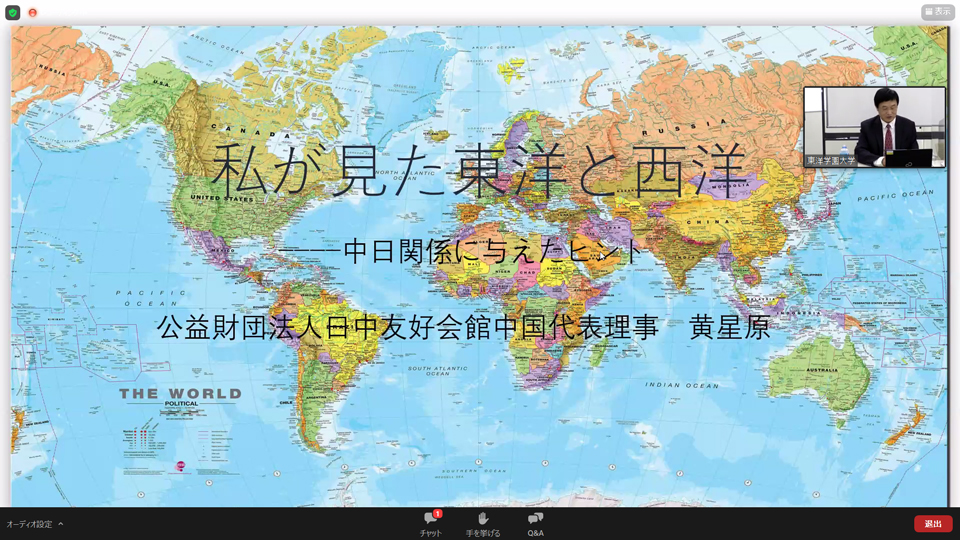
一般財団法人ユーラシア財団 from Asiaの助成による特別講座「我々は『ステークホルダー』−アジア共同体の新しい視角」(科目名:アジアの社会と文化)。
10/8(金)に行われた第4回には、公益財団法人日中友好会館中国代表理事の黄星原氏をお招きしました。
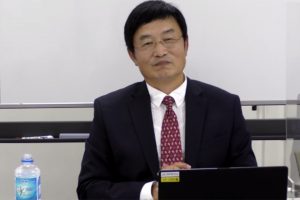
公益財団法人日中友好会館中国代表理事 黄星原氏
黄氏は12年間にわたる在日中国大使館勤務を経て、トリニダード・トバゴおよびキプロス大使を歴任。その長年の外交官としての経験から東洋と西洋の文化、そのはざまに立つ日本と中国の関係について知見を披露しました。
まず、世界を席巻しているコロナ禍を例に、中国人民外交学会、アメリカ外交学会、そして日中友好会館という3つのシチュエーションで講義を行った場合を想定。中国、アメリカ、日本それぞれの国情と文化の違いがコロナ対策に大きな差をもたらしたことを指摘しました。

東洋思想や漢方の流れを汲む中国では命を重んじる施策がとられ、国民の生活に一定の制限をかけつつコロナの封じ込めに成果を上げました。一方、個人の自由を重んじるアメリカではそれが枷となり、専門家の意見さえスルーされて世界最悪の結果をもたらしています。そして日本は、規律を重んじる国民性がマスクの着用などに効果を上げましたが、他国にゆだねたワクチン供給のせいで、コロナのコントロールに苦慮することになりました。それは日本人が体は東洋で、心は西洋であるという、そのはざまで揺れ動いているからであると黄氏は考察します。

次いで黄氏は日本、トリニダード・トバゴ、キプロスでの外交官時代に得た知見に論を転じます。共通するのはいずれも島国であり、隣国に大国があり、気候変動や安全保障に敏感であるということ。そのなかでトリニダード・トバゴとキプロスは対極にあったと語ります。
トリニダード・トバゴは周辺諸国と良好な関係を維持することが自国の利益につながると考え、アメリカへの天然ガスの輸出、日本からの自動車の輸入、中国からのインフラ支援がそれぞれ約7割を占めるなど、複数の大国と一定の関係を維持しています。
一方キプロスは、英国軍の駐留など大国への過信が、1974年のトルコ侵入を許し、現在も国土の36%をトルコが占有する事態となっています。
日本に目を転じると、安全保障や台湾問題などに敏感ではあるものの、アメリカと対立関係にあるといわれる中国とも友好的な協力関係を維持しています。日本人の考え方は中庸で、バランスがとれている、と黄氏は語ります。
もっとも印象的なのは、四川大地震時に日本は中国に大きな支援を行い、東日本大震災では真っ先に中国が援助隊を送るなど、危機的状況下での互いの行動。
山川異域風月同天(山川は異なるが風月は同じ天の下)
中国でコロナが猖獗を極めているときに、日本から援助されたマスクの箱に書かれていた言葉は、中国国民に大きな感動と感謝の念をもたらしたそうです。

さらに黄氏は大きな影響を受けた日本人3人について述べました。一人は雲南省の県副知事時代に知遇を得たNHK記者の加藤高広氏。若くして亡くなったその遺志を受けて中国辺境地に小学校が建設され、以来、何千人もの児童に教育が施されているといいます。さらにその思想にかかわらず、中国訪問後に公平な目で中国を再評価した石原慎太郎氏。歴史を直視し教訓をくみ取った中曽根康弘氏。立場や思想を異にする人々との交流、大使としての経験を踏まえて、最後に以下のように結論付けました。

黄氏の語った結論は、「東洋と西洋の文明や文化がどのように違っても、アジアの大国としての中国と日本は、ともに手を携えてアジア全域の発展と平和に寄与することが求められている」ということ。
日中両国の協力がアジアの繁栄をもたらす、と受講生に語り掛けました。
今年度は2022年1月まで全14回にわたり、様々な講師を招くオムニバス形式で開講。
一般の方々もZoomウェビナーで聴講が可能です。
次回は10/22(金)、講師にZTE副総裁の張林峰氏を迎え、「5Gの世界と世界の5G」というテーマで実施します。
講座の詳細や参加申し込みはこちら
